マンションの防水工事にかかる費用の税金に関する見解は国税庁や税務署が状況次第で判断していますが、できるだけ節税したいと考える人が多いと思います。
しかし屋上防水工事やベランダ防水工事をした際の費用をうまく減価償却できずに節税するつもりが、納税額が多くなってしまうことも。
- マンションの防水工事に関する法定耐用年数の基本ルールはどうなっているのかについて。
- マンションの防水工事に関する費用について国税庁が認めている減価償却ルールと判断基準について。
- マンションの防水工事で減価償却や節税対策で失敗して税負担が増える代表的なパターンには何があるのかについて。
- マンションの防水工事の費用をうまく節税するためのポイントと対策について。
- マンションの防水工事で減価償却や節税対策に失敗したくない人向けのよくある質問まとめ。
屋上防水工事もベランダ防水工事もマンションの資産価値を維持して、入居者の満足度を低下させないためにも必要なことですよね。
同じ防水工事を行った場合でも、見積書や契約書の書き方、工事範囲の記載方法によっては思ったような節税対策にならないことも。
この記事ではマンションの防水工事にかかった費用の減価償却や節税対策に失敗するのはどんな状況が多いのかという点について紹介しますので、賢い節税対策をして適切な納税をしたい人は参考にしてください。
マンションの防水工事に関する法定耐用年数の基本ルールはどうなっているのか?
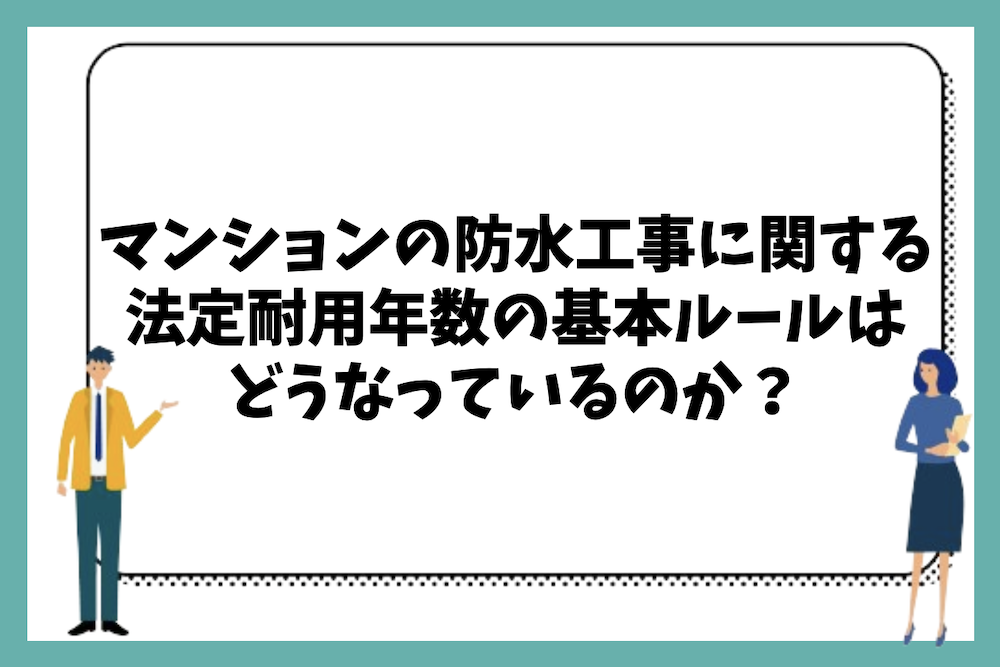
マンションの防水工事に関する法定耐用年数の扱いは、税務や会計の観点から見ても非常に重要なことです。
法定耐用年数や減価償却に関する正しい情報を理解することが、結果的に適切な節税対策に繋がりますのでしっかり確認しておいてください。
国税庁が定める法定耐用年数制度の基本ルールがマンションの防水工事にどう当てはまるのか紹介しますので、基本知識として覚えておきましょう。
国税庁が定める法定耐用年数とはどのような考え方をすればよいのか?
まず最初に法定耐用年数がどういったものかというと、国税庁が定めた減価償却資産が使用に耐える年数(税務上の寿命)のことです。
建物や設備、機械などの資産は、買った年にすべてを経費にすることができるわけではなく、法定耐用年数に応じて毎年少しずつ経費にしていく(減価償却)しなければならないという仕組みになっています。
国税庁はマンションの防水工事を単体の資産ではないと考えている。
マンションの防水工事(屋上防水工事やベランダ防水工事)は、設備機器や車両のように単体で減価償却資産として登録されることは基本的にはありません。
防水層は建物の一部であり、それ自体が独立して価値を持つモノと国税庁が判断していないから。
マンションの防水工事に関する費用は下記のいずれかで処理する必要があります。
| 処理区分 | 内容 | 耐用年数の扱い |
| 修繕費 | 建物の機能を維持 回復する補修工事 | 一括で経費処理 (耐用年数の概念なし) |
| 資本的支出 | 建物の性能向上 寿命延長となる改修工事 | 建物本体と同じ耐用年数 (または残存年数)で償却 |
国税庁が定義している建物ごとの法定耐用年数はどうなっているのか?
国税庁が定める耐用年数表によると、建物の種類ごとに下記のような法的耐用年数が定められています。
| 建物の構造 | 用途 | 法的耐用年数 |
| 木造・合成樹脂造の建物 | 住宅・非住宅 | 22年・24年 |
| 軽量鉄骨造(骨格厚3mm以下) | 住宅・非住宅 | 19年・17年 |
| 重量鉄骨造(骨格厚3~4mm) | 住宅・非住宅 | 27年・34年 |
| RC造 鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC) | 住宅・非住宅 | 47年・50年 |
*マンションはほとんどがRC造のため、法的耐用年数47年が基準となると理解しておいてください。
マンションの防水工事に関する費用について国税庁が認めている減価償却ルールと判断基準は?
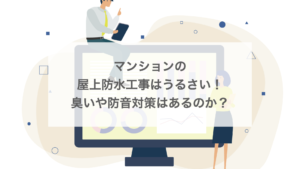
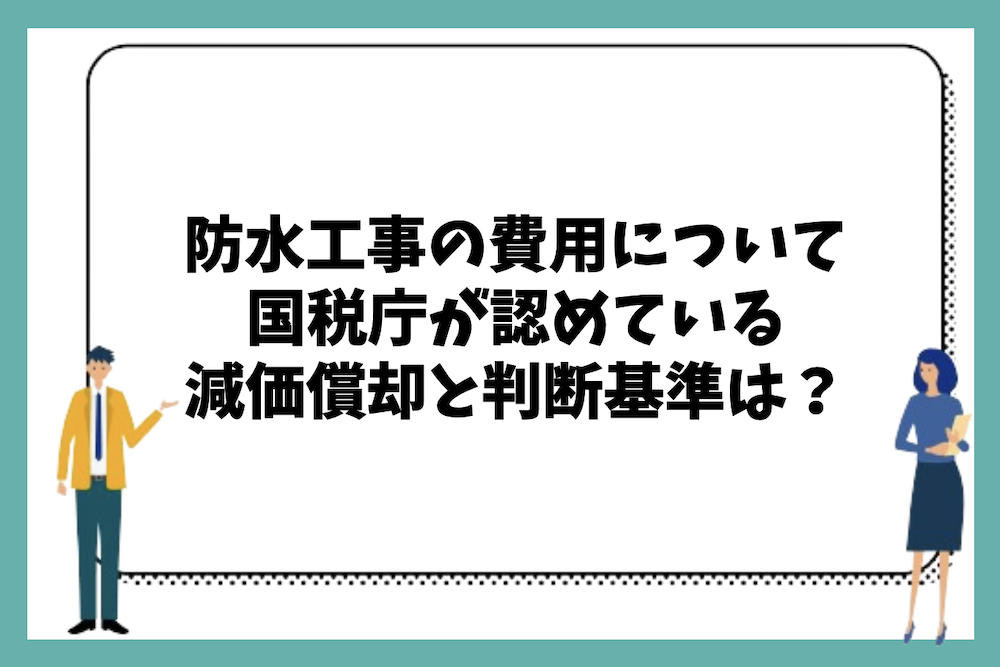
マンション防水工事の費用に関して国税庁が認める減価償却ルールとその判断基準は、法人税法および国税庁の通達(法人税基本通達7-8-1)に基づいて細かく定められているのをしっていますか?
この通達では、建物の修繕や改良などに関する支出が修繕費(一括経費)か資本的支出(減価償却)かを明確に区別しており、その判断に応じて処理方法が異なります。
修繕費と基本的支出の違いを理解していないと、防水工事の費用をうまく経費計上できませんので、しっかり確認しておいてください。
マンションの防水工事費用の税務処理をする際に理解すべき2つの区分とは?
繰り返しになりますが、国税庁はマンションの防水工事に関する費用を次の2つのいずれかに区分して税務処理するよう定めています。
| 区分 | 内容 | 税務処理 |
| 修繕費 | 建物の機能を維持 回復する工事 | 工事を実施した年に 一括で経費化 |
| 資本的支出 | 建物の価値を高めたり 寿命を延ばす工事 | 減価償却の対象 複数年に分けて経費処理 |
どちらの区分にするかによって税負担が大きく変わるため、慎重な判断が必要です。
国税庁が法人税基本通達7-8-1を理由に修繕費と基本的支出をどのように判断しているのか?
法人税基本通達7-8-1では、修繕費と資本的支出の違いを次のように定義していますので、その基準に従って税務処理する必要があります。
国税庁や税務署にマンションの防水工事が修繕費とされる主な条件は?
- 原状回復・機能維持を目的とした補修工事
- 工事内容が過去の実績・標準的な水準を超えていない
- 高価値化や延命効果が見込まれない
具体的には、屋上やベランダの防水層の再塗装(トップコートのみ)、漏水を防ぐための部分補修、老朽化した防水材の「同等品」への張り替え(性能向上でなければOK)などが修繕費と判断され、その年度に全額損金として算入することが認められています。
国税庁や税務署にマンションの防水工事が資本的支出とされる主な条件は?
下記のいずれかの項目に該当する場合は、資本的支出(減価償却)として処理しなければなりません。
| 資本的支出の代表的なケース | 国税庁が定める判断基準例 |
| 建物の機能を高めるもの | 従来よりも高性能な防水素材を使用して、 断熱性や耐久性が著しく向上した場合など |
| 使用可能期間の延長 | 工事で建物の寿命が延びると判断されるケース (補強・補填の範囲を超える) |
| 50万円超の増築・改良 (合理的に区分できる部分に限る) | 施工範囲が明確で独立性のある部分であれば 高額支出は減価償却の対象となる |
| 過去に存在しなかった防水機能の新設 | 元々防水処理のなかった箇所に 新たに防水層を設けた場合など |
上記に該当する場合は資産の取得とみなされるので、建物と同じ耐用年数(または残存年数)で償却する必要があります。
マンションの防水工事に関する減価償却のルールとその適用方法は?
マンションの防水工事が資本的支出と判断された場合、下記ルールに従って減価償却処理を行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
| 償却資産の種類 | 建物の附属設備か建物本体扱い (用途や内容による) |
| 耐用年数の算出方法 | 建物の法定耐用年数−経過年数=残存耐用年数 |
| 償却方法 | 定額法または定率法 (個人・法人で選択肢が異なる) |
| 償却開始時期 | 工事が完了した日 (資産として利用可能になった日)から開始 |
上記に該当する場合は資産の取得とみなされるので、建物と同じ耐用年数(または残存年数)で償却する必要があります。
例:RC造マンション(耐用年数47年)で防水工事300万円、築20年の場合は?
上記条件に該当する内容で防水工事を行った場合に基本的支出として判断されたら、どのような計算をして減価償却していく必要があるのかというと、
- 残存耐用年数:47年−20年=27年
- 年間の減価償却費:300万円÷27年=約11.1万円
- 定額法の場合は、上記金額を毎年経費に計上していく必要があります。
法人税基本通達7-8-1が基準になりますので、物件オーナーや管理会社が勝手に判断して、修繕費か基本的支出かを判断できないことは十分に理解しておいてください。
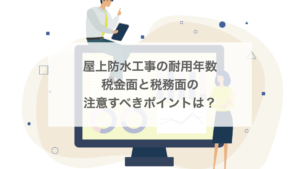
マンションの防水工事で減価償却や節税対策で失敗して税負担が増える代表的なパターンは何があるのか?
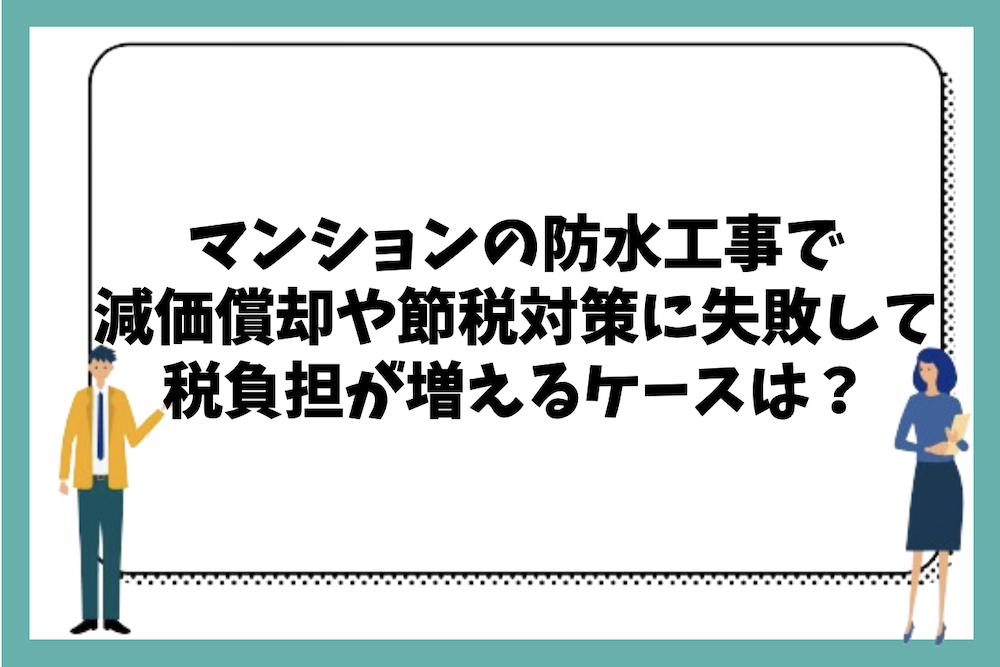
ここまで説明してきたようにマンションの防水工事にかかった費用をどのように処理するかによって、十分に節税できるのか、それとも減価償却が必要になるのかが大きく分かれます。
節税できると思っていたのにできなかった人や減価償却で損したという失敗例も多いので、どうすれば良かったのかが気になる人もいるのではないでしょうか。
どのような失敗例が多いのかというと、
- 修繕費のつもりが資本的支出だと判定されてしまった。
- 建物の残存耐用年数が長すぎて償却負担が重くなった。
- 修繕費として処理したのに税務調査で否認されてしまった。
- 節税目的でまとめて工事したけど少額資産の特例が使えなかった。
- 工事のタイミングが悪くて節税効果を十分に活かしきれなかった。
上記がマンションの防水工事の費用について、減価償却や節税対策で失敗しがちなケースになります。
何が失敗の原因だったのか、どのようにすればよかったのかなど少しでも節税効果を高めたい人は、失敗例を参考にしてください。
修繕費のつもりが資本的支出だと判定された│防水工事費用節税の失敗例
マンションの防水工事を経費として一括処理したつもりだったのに、税務署から、資本的支出だと指摘されて減価償却のやり直しを求められた。
結果として経費計上できる金額が少なくなり、法人税と所得税の負担が増加することになった。
マンションの防水工事費用の節税が失敗した原因は?
- 工事の内容が性能向上や新設工事とみなされるような表現で記載されていた。
- 具体的には見積書に高耐久化や長寿命化、高機能といった文言があった。
- 実質的に建物の使用可能期間が延びているような内容となっていた。
どう対策すれば失敗せずにうまく節税することができたのか?
- 工事の目的を原状回復や維持補修であることを文書で明確にする。
- 見積書や契約書を部分補修や劣化箇所の修復といった記載に変更する。
- 工事を行う前に税理士と相談して資本的支出と判断されるリスクを把握する。
建物の残存耐用年数が長すぎて償却負担が重くなった│防水工事費用節税の失敗例
例えば、築10年のRC造マンション(耐用年数47年)だと法定耐用年数の残存期間が37年ほどになります。
その建物で500万円ほどの大規模な防水工事を行った結果、年間で13万円程度しか経費にできずに思ったよりも節税効果を得られなかった。
マンションの防水工事費用の節税が失敗した原因は?
- 減価償却による節税効果は時間分散されるために初年度に期待したような節税効果を実感できない。
- 工事の規模が大きすぎて分割処理するしか選択肢がなくなってしまった。
どう対策すれば失敗せずにうまく節税することができたのか?
- 一括500万円の工事を1年で100万円×5年というような複数年に分けて少額の分割工事にする。
- 補修レベルの小規模工事に変更して修繕費として一括経費にする。
- 築年数が古くて残存耐用年数が短い物件の方が節税効果が大きくなる点を考慮する。
修繕費として処理したのに税務調査で否認された│防水工事費用節税の失敗例
確定申告や決算書で修繕費として処理していたマンションの防水工事費用が、後の税務調査で資本的支出と判断されて追徴課税を支払わなければならなくなった。
マンションの防水工事費用の節税が失敗した原因は?
- 見積書や契約書の施工内容が改良とも解釈できる文面だった。
- 写真や報告書に新品交換や全面防水、断熱強化などの記述があった。
- 証拠資料を残していなかったため修繕費としての正当性を証明することができなかった。
どう対策すれば失敗せずにうまく節税することができたのか?
- 見積書や施工報告書、写真などの資料を工事前から記録としてしっかり残しておく。
- 修繕目的であることを契約書に明確に明記しておく。
- 経理処理の記録を整えて説明責任を果たせるようにしておく。
節税目的でまとめて工事したけど少額資産の特例が使えなかった│防水工事費用節税の失敗例
どうせやるならまとめて工事した方がお得だと考え、一括で500万円分の防水工事を実施したが、1件30万円を超えてしまった。
その結果、中小企業向けの少額減価償却資産の即時償却特例(30万円未満)を使うことができなくなってしまった。
マンションの防水工事費用の節税が失敗した原因は?
- 工事項目がまとめて1契約になっていた。
- 一式工事扱いなど見積書が分かれていなかった。
- 分割可能な工事だったが、帳簿上ではひとまとめに処理されてしまった。
どう対策すれば失敗せずにうまく節税することができたのか?
- 工事項目を用途や場所ごとに分割して、1項目あたり20~30万円未満になるよう設計しておく。
- 防水トップコートのみ、排水口まわりの補修のみなどに区分して申請する。
- 税理士と一緒に分割可能な工事かを事前確認、相談しておく。
工事のタイミングが悪くて節税効果を十分に活かしきれなかった│防水工事費用節税の失敗例
利益が出ている年に工事を実施すれば節税効果が高かったのに、赤字の年に工事を行ってしまい、減価償却費が節税効果を発揮できなかった。
マンションの防水工事費用の節税が失敗した原因は?
- 節税目的での工事タイミング戦略を考慮していなかった。
- 決算対策としての計画性がなかった。
どう対策すれば失敗せずにうまく節税することができたのか?
- 年間収益の見通しを踏まえて、利益が多い年に合わせて工事を実施する。
- 必要に応じて、複数年に分けて工事するという方法も検討する。
マンションの防水工事で減価償却や節税に失敗する主なケースを一覧にまとめると、
| 失敗パターン | 原因と税務リスク | 対策 |
| 修繕費のつもりが 資本的支出になった | 工事の内容や表現が 性能向上に見える | 工事目的と記載内容を 事前に精査する |
| 残存耐用年数が長く、 経費化が進まない | 長期償却で初年度の 節税効果が低い | 小規模工事に分割 築古物件の方が有利 |
| 税務調査で否認される | 曖昧な書類・証拠不足 | 見積書、契約書、 報告書の記録を整備 |
| 少額資産特例を 使えなかった | 工事一式で 30万円以上の処理 | 工事項目を分けて 見積書を調整する |
| タイミングが悪く 節税効果を活かせなかった | 赤字決算の年に 防水工事をしてしまった | 利益が出る年度に合わせて 防水工事を実施する |
上記のような失敗例が多く報告されていますので、マンションの防水工事の費用の節税効果を実感したい人は、間違っても同じようなことを行わないようにしてください。
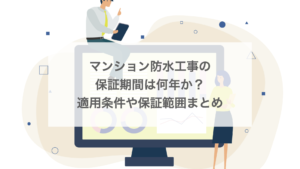
マンションの防水工事の費用をうまく節税するためのポイントと対策は?
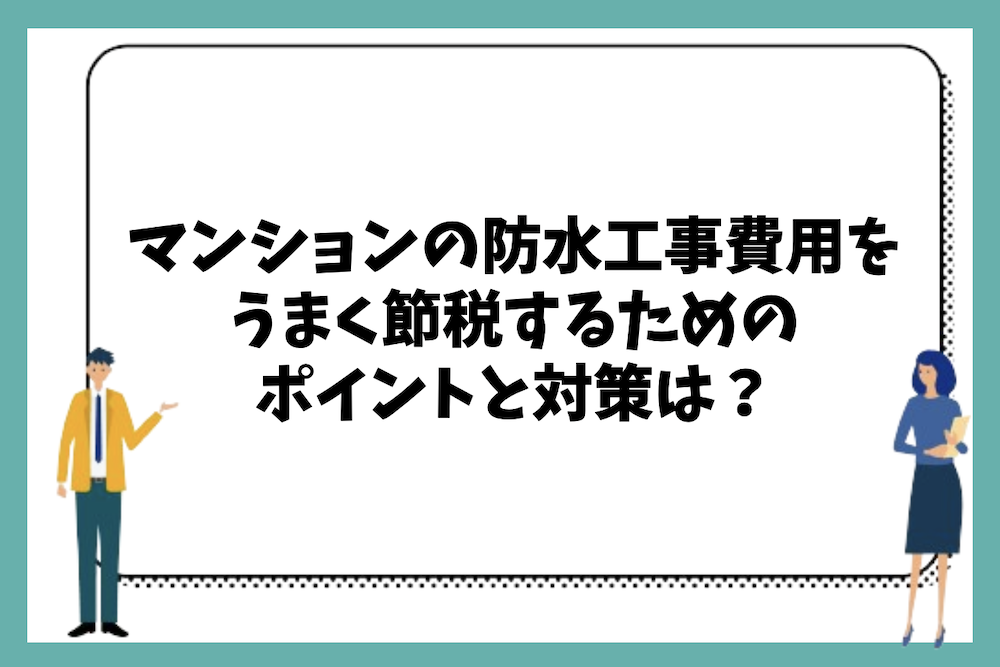
マンションの防水工事は金額が大きくなりがちな一方で、税務処理の仕方によっては大きく節税できるチャンスだということもできます。
ただ工事内容や見積書の記載内容、会計処理方法を間違えると、思ったより節税効果が出なかったり、税務調査で否認される可能性も。
後で後悔しないためにもマンションの防水工事の費用をうまく節税するための具体的なポイントと節税対策について、国税庁の通達や実務に基づいて解説しますので、防水工事を行う際の参考にしてください。
節税のポイントは、防水工事費用を修繕費として一括経費にできるかどうかで決まる。
マンションの防水工事費用は、税務上で2種類の処理方法があり、修繕費として処理することができればその年の経費として一括計上することができます。
| 区分 | 内容 | 節税効果 |
| 修繕費 | 建物の機能維持 原状回復のための工事 | 全額をその年の経費にできる |
| 資本的支出 | 建物の寿命を延ばす 価値を上げるような工事 | 減価償却で数年に分割 (節税効果が分散される) |
マンションの防水工事費用が修繕費として認められるために必要な4つのポイントは?
マンションの防水工事費用が修繕費として認められるためには下記4つのポイントを満たす必要があります。
具体的にどのようなことに注意すればよいのかというと、
- 工事目的を原状回復と明確にしておく。
- 工事内容が高性能化とならないよう注意する。
- 見積書や契約書は細かく分けて記載する。
- 工事費用を30万円未満に抑えて、少額資産特例を活用する。
上記内容に注意してマンションの屋上防水工事やベランダ防水工事を行うことで、節税効果を実感することができますので、それぞれ項目ごとに詳しく説明していくと、
防水工事の目的を原状回復と明確にしておく│修繕費の要件
劣化した防水層の補修や従来通りの仕様での再施工など、現状維持や機能回復を目的としていることを、契約書や見積書、施工報告書に明記します。
- 既存ウレタン防水層の同等品による再施工
- トップコートの剥離箇所を部分的に補修
- 新たな断熱材の追加や高性能仕様の導入は行わない
防水工事の内容が高性能化とならないよう注意する│修繕費の要件
下記のような文言が見積書や契約書にあると、資本的支出とみなされる可能性が高まりますので、記載しないように注意します。
- 高耐久型材料による全面改修
- 断熱・遮熱性能の大幅な向上
- 既存機能を超える改良施工
節税効果を実感するためには、あくまでも現状仕様を維持する補修であることを強調しておく必要があることを理解しておきましょう。
防水工事の見積書や契約書は細かく分けて記載する│修繕費の要件
防水工事の内容を修繕費として処理するためには、見積書を下記のように細かく分類するのが理想的です。
| 工事内容 | 工事費用 | 備考 |
| 防水トップコートの再塗装 | 15万円 | 修繕費として一括経費可 |
| ドレン清掃・排水溝補修 | 5万円 | 維持目的なので問題なし |
| 防水層の全面高性能ウレタン化施工 | 45万円 | 資本的支出になる可能性大 |
工事内容を項目ごとに分類して記載することで、修繕費と資本的支出の合理的な区分が可能になります。
中小企業は防水工事費用を30万円未満に抑えて少額資産特例を活用する│修繕費の要件
中小企業や青色申告をしている個人事業主だと1件30万円未満の工事費用であれば、全額をその年の経費にできるという特例(少額減価償却資産の即時償却)を使うことができます。
| 条件 | 内容 |
| 対象者 | 中小企業者(資本金1億円以下など) |
| 上限金額 | 1年間で合計300万円まで |
| 資産1件あたりの金額 | 取得価額が30万円未満であること(税抜き) |
防水工事を複数の小項目に分割して、それぞれの費用が30万円未満であれば、工事費用の全額を即時償却することができて節税効果が高まります。
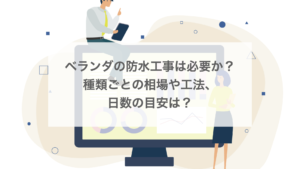
マンションの防水工事で減価償却や節税対策に失敗したくない人向けのよくある質問まとめ。
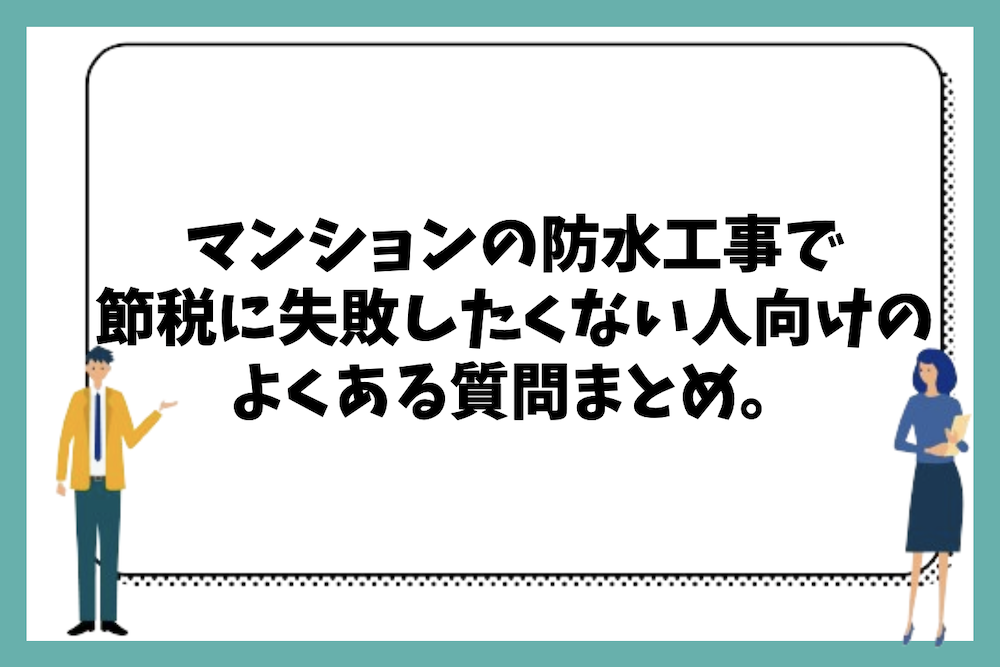
ここまで説明してきたようにマンションの防水工事は事前にしっかり準備して行うことで、十分な節税効果を実感することができることがわかったと思います。
事前準備を怠り、突発的な防水工事が必要になった場合では、減価償却ルールが適用されてしまい想定以上に法人税や所得税を支払わなければならなくなる場合も。
マンションの防水工事費用は修繕費か基本的支出のどちらで処理しなければならないかによって節税効果が大きく異なりますので、失敗して公開しないためにもよくある質問を紹介しておきますので、マンションの防水工事の準備をする際の参考にしてください。
マンションの防水工事費用を減価償却しなければならない場合に節税効果が薄れるのはなぜですか?
減価償却とは、資本的支出として分類された工事費用を複数年にわたって経費化していく処理方法です。例えば500万円の工事費用をRC造の建物(耐用年数47年)で償却する場合、1年あたりの経費は約10.6万円しか認められません。減価償却ルールが適用されると、当期の利益に対してほとんど節税効果が出ないために修繕費として処理できる工事と比べて税務上のメリットが小さくなります。短期的な節税効果を狙うなら、工事の内容や書面の記載を工夫して、なるべく修繕費扱いを目指すのが得策ではないでしょうか。
マンションの防水工事の見積書をどのように作成すれば節税しやすくなりますか?
マンションの防水工事を行う際に節税を意識した見積書を作りたい場合は、工事内容を項目ごとに細かく分けることが重要になります。例えば、防水トップコートの再塗装や排水口まわりの清掃、部分補修といった作業を分割して記載することで、修繕費と資本的支出を合理的に区分することができます。特に20万円未満や30万円未満の工事については、少額資産特例の適用が可能になるため、節税効果を強く実感できるでしょう。逆に、工事一式としてまとめて記載してしまうと、資本的支出とみなされるリスクが高まり節税効果を実感できないことを理解しておいてください。
マンションの防水工事を行う際に節税に強い業者や税理士を選ぶにはどうすればよいですか?
マンションの防水工事の節税対策を高めるためには、施工業者や税理士が税務処理に精通していることが重要なポイントになります。施工業者には見積書や契約書の記載を修繕費として処理ために有利な内容に調整してもらえるかを確認したり、過去の事例や対応実績を聞けば大まかな判断はできます。税理士には、工事内容を元に修繕費か資本的支出かを適切に判断できる経験があるかがポイントになります。できれば建築や設備投資に詳しい専門税理士を選び、事前相談から書類作成まで一括したサポートを依頼することで、安心して節税効果を実感することができると思います。
マンションの防水工事を建物附属設備として処理できるのはどんな条件に該当する時ですか?
マンションの防水工事が建物附属設備として独立資産と認められるのは非常ににまれなことで、ほとんどの場合は建物本体の一部と見なされます。ただ防水設備が特別な機能を持っていることで、建物と切り離して使用可能であると判断されれば、独立資産として耐用年数15年(建物附属設備の一般例)で処理できる可能性もあります。一般的なマンションの屋上防水やベランダ防水は建物構造と一体化していることが多いため、基本的には建物本体としての減価償却しかできません。節税目的での資産区分は慎重に行う必要がありますので、税理士にも確認をとってから最終的な判断を行ってください。
マンションの防水工事を個人事業主が行う場合の減価償却の注意点は何がありますか?
個人事業主がマンションを賃貸経営していて防水工事を行った場合、その工事が資本的支出であれば、建物と同じ残存耐用年数で減価償却する必要があります。個人事業主の減価償却方法は原則として定額法が採用され、法人に比べて節税の幅がやや狭くなることがあります。また建物の取得価額に含めて処理する必要があるケースや耐用年数の計算に特例が適用される場合もあるため、防水工事の見積書や建物の登記内容をもとに正確な処理を行うことが重要です。確定申告前には必ず専門家に相談をすることで余計な税務調査を避けることができます。
マンションの防水工事費用は自治体の補助金を受けた場合でも経費にすることができますか?
マンションの防水工事に対して自治体の補助金を受けた場合、その補助金額分は原則として工事費用から控除する必要があります。例えば500万円の工事費に対して100万円の補助金を受けた場合、減価償却や修繕費として処理できる金額は実質負担額の400万円になります。補助金は収入として計上されることが多いため、結果的に帳簿上の利益が増加して節税効果が薄まることがあります。補助金申請時には、税務処理との整合性も考慮して支出額との相殺方法を税理士等に確認することも大切です。
マンションの防水工事を管理組合で実施した場合は税務上どう処理すればよいのか?
マンション管理組合として実施した防水工事は、基本的に共用部分の修繕として扱われますので、管理組合会計上は修繕費として計上することになります。ただ区分所有者の確定申告においては、管理組合が工事を実施しただけでは個別の経費とは認められず、各区分所有者が負担した修繕積立金が特定工事に使われたかどうかが判断材料となることを理解しておいてください。特に賃貸用住戸を所有している場合、工事費が個別負担となっていれば損金処理の対象になり得るために管理組合からの通知や工事報告書をしっかり保存しておくようにしてください。
マンションの防水工事費用の節税目的で工事時期をずらすのはアリかナシか?
節税目的でマンションの防水工事の実施時期を調整するのは、合法かつ有効な税務戦略のひとつです。例えば利益が出る年度に工事を行って修繕費として計上すれば課税所得を大きく圧縮できるため、法人税や所得税の節税に直結します。逆に赤字決算の年に高額な修繕費を使っても、税負担は変わらず効果が薄まる可能性が高いでしょう。防水工事が差し迫っていないのであれば、決算前に税理士と利益予想を元に最適な工事タイミングを検討することをおすすめします。
マンションの防水工事費用が高額すぎると税務上不利になることがあるのか?
マンションの防水工事の金額が大きくなりすぎると、税務上では資本的支出と見なされる可能性が高くなりますので、不利になると理解しておくべきでしょう。例えば一括で500万円以上の防水工事を行った場合、その内容が高機能化や全面改修だと判断されると減価償却の対象となり、数十年にわたって分割経費化せざるを得なくなります。このようなケースでは、短期的な節税効果は薄れてしまい期待していたような節税効果を実感できない恐れがあります。節税を重視するなら、大規模工事でも可能な限り工事項目を分割して修繕費や少額資産扱いにできる範囲を最大化することが有効的です。
マンションの防水工事費用に関して、減価償却と修繕費の両方を使うことができるのか?
1つの防水工事においても、修繕費として処理できる部分と資本的支出として減価償却する部分が合理的に区別できれば、法人税基本通達7-8-1(2)でもそれぞれ別個に処理することが認められています。例えば、ベランダのトップコート再塗装(修繕費)と、屋上全体の防水層の新設(資本的支出)という具合に見積書に区分を設けることで、節税効果を最大化することもできます。ただ見積書や契約書など書類上の記載があいまいだと、全体が資本的支出とみなされる可能性があるので、事前にしっかり確認するようにしてください。
当コンテンツでは、税務処理に関する情報を一般的な事例や国税庁の公開資料に基づいてご紹介していますが、個々の状況によって適用される税法や会計処理は異なる場合があるので、あくまでも参考情報としてご理解ください。
税務上の取り扱いや申告に関する相談や判断は、税理士などの有資格者にご相談いただくことをおすすめします。
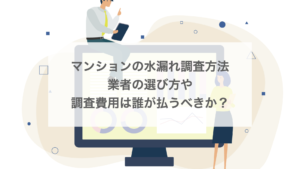
外壁の劣化状態の確認や修繕工事費用の無料見積もりはフェアリノベーション株式会社にお任せください。
マンションやアパートの外壁診断やリフォームに関することであれば、どのような相談でもお受けすることができます。
フェアリノベーション株式会社の外壁診断のおすすめポイント!
- 外壁診断のお見積もりは無料です。
- 訪問なしでお見積もりが可能です。
- 親切丁寧な対応が評判です。
- 疑問点は何度でも相談できます。
将来的な大規模修繕工事や外壁調査を検討されている方でも良いので、現状確認の為にもまずはお気軽にご連絡ください。

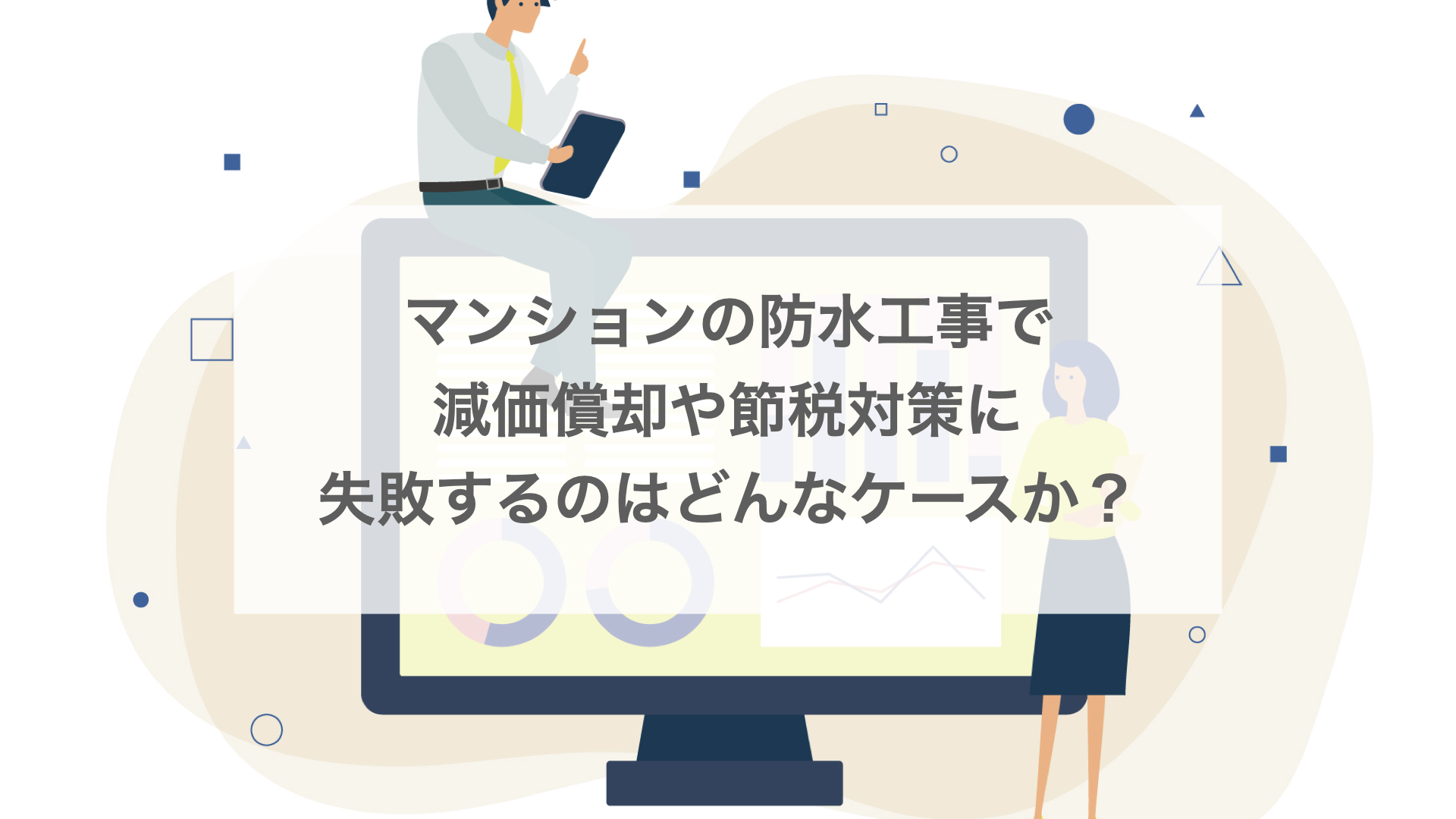
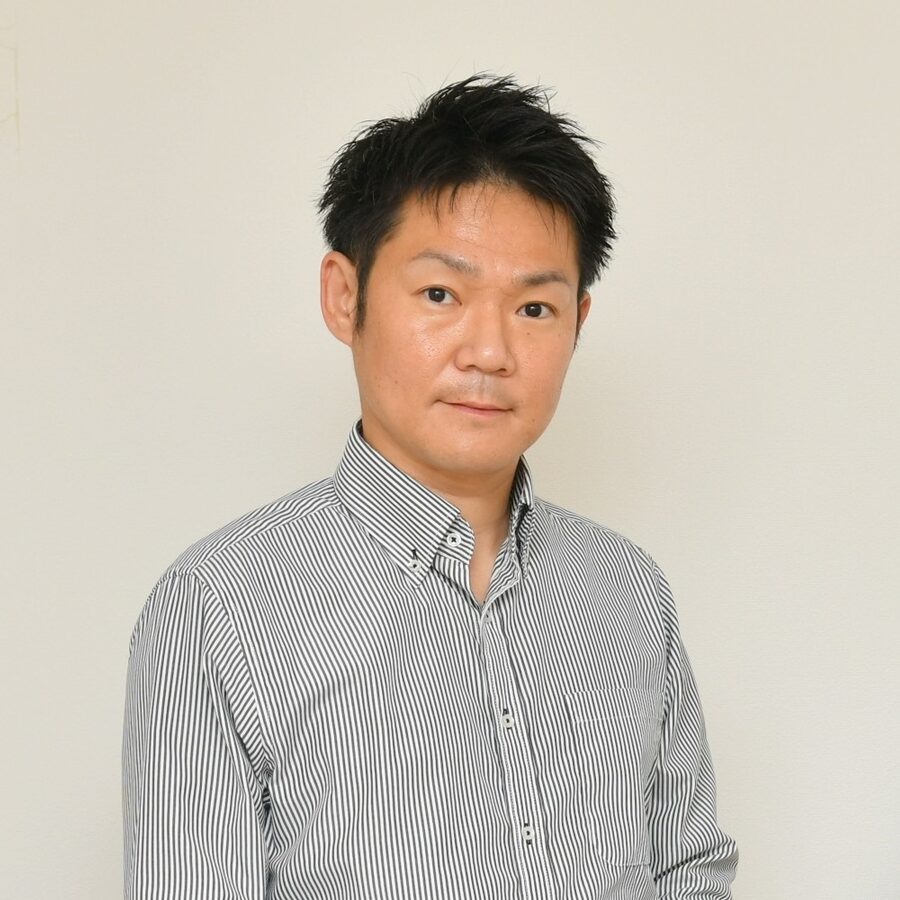
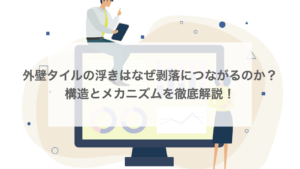
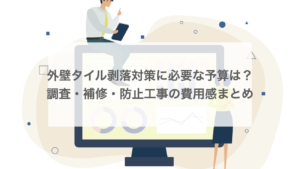
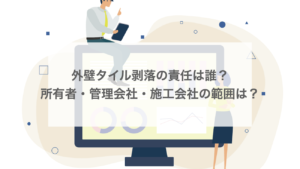
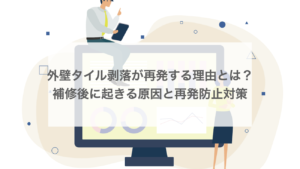
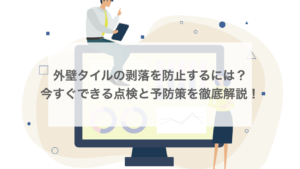
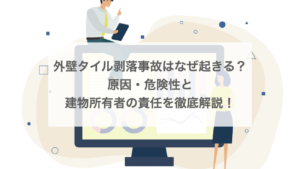
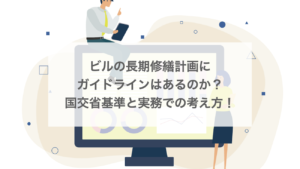
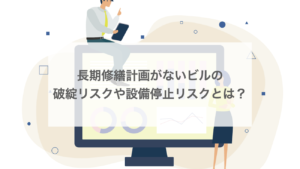
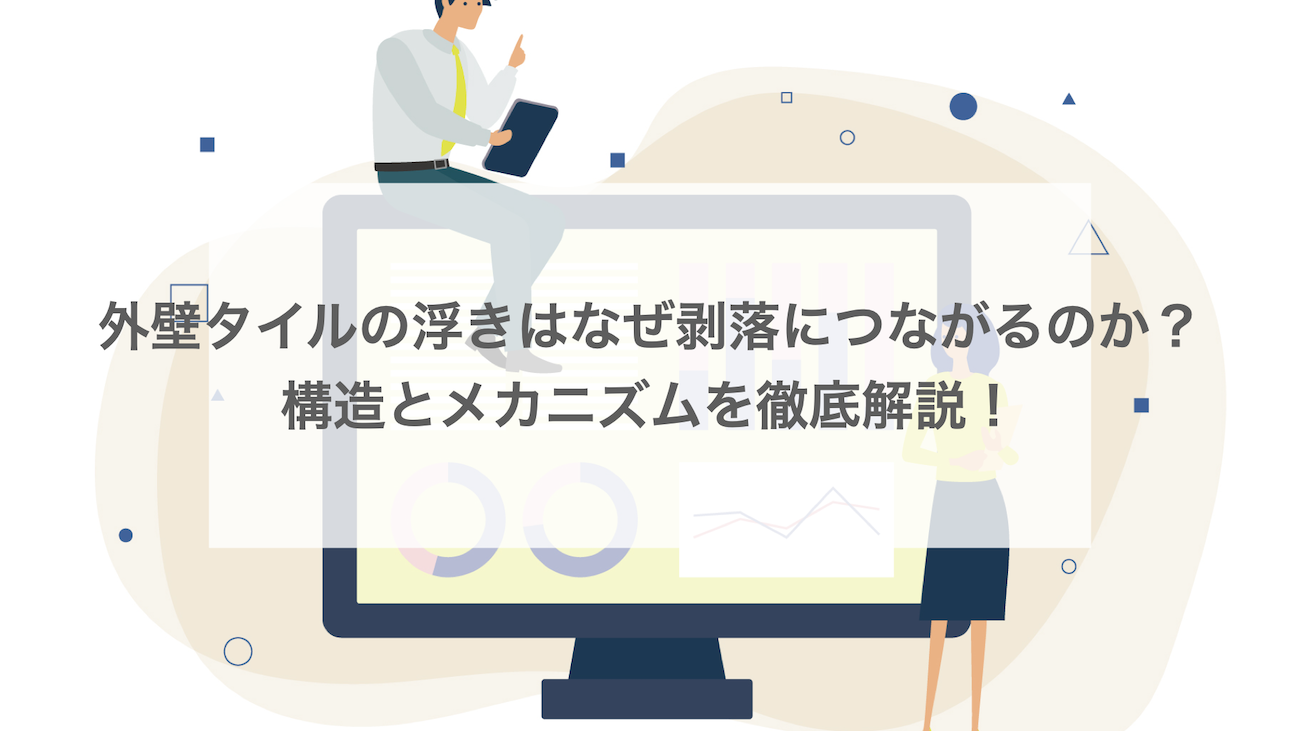
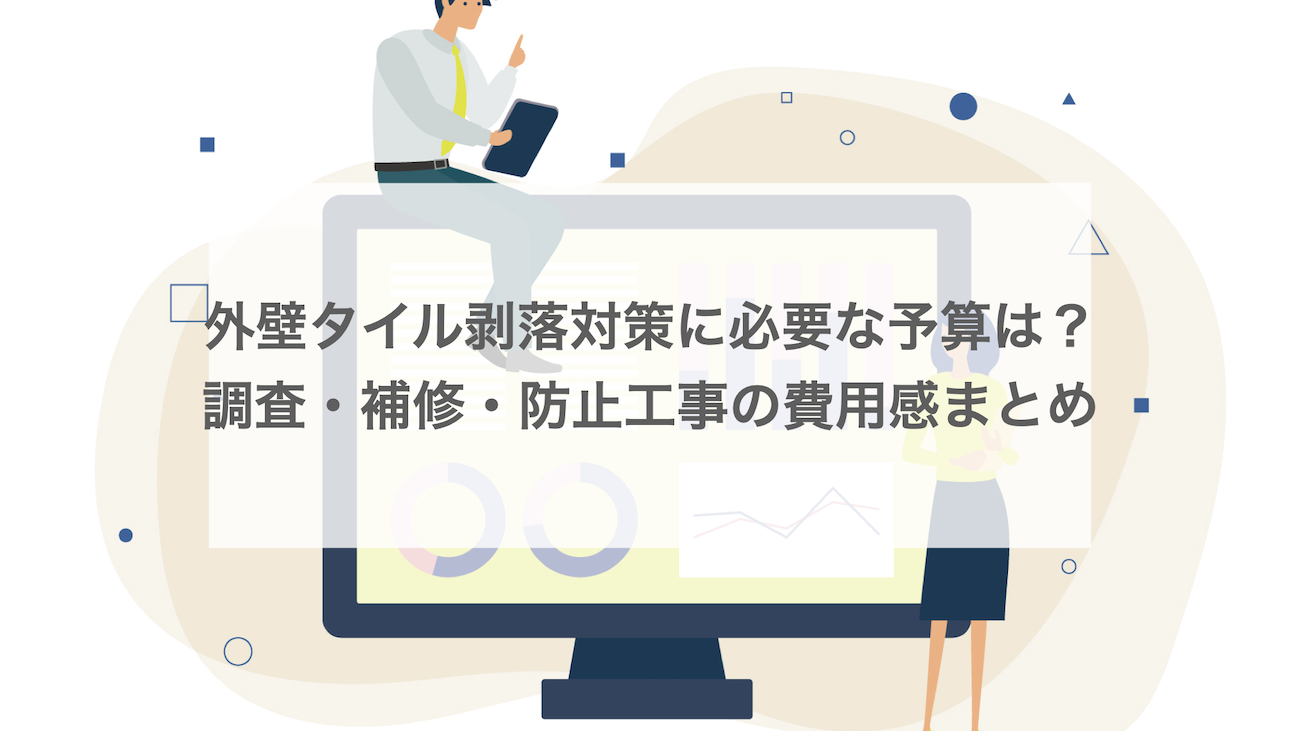
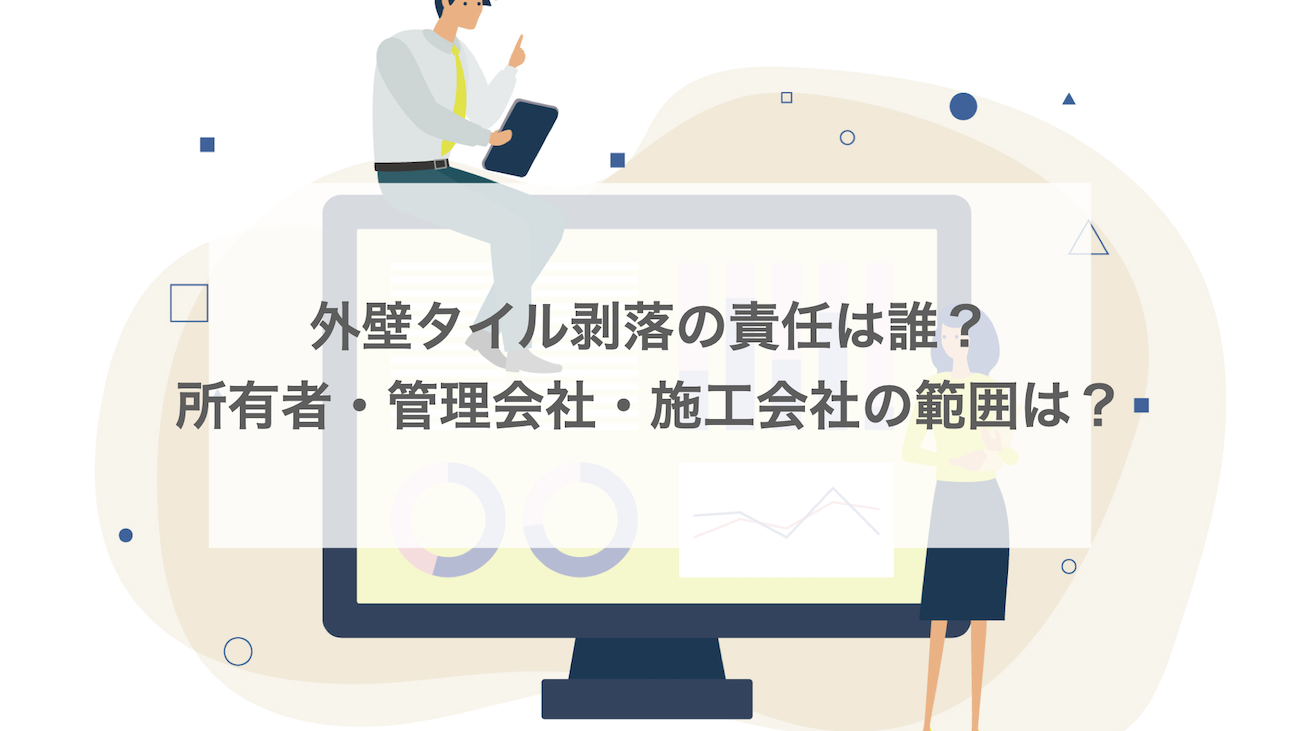
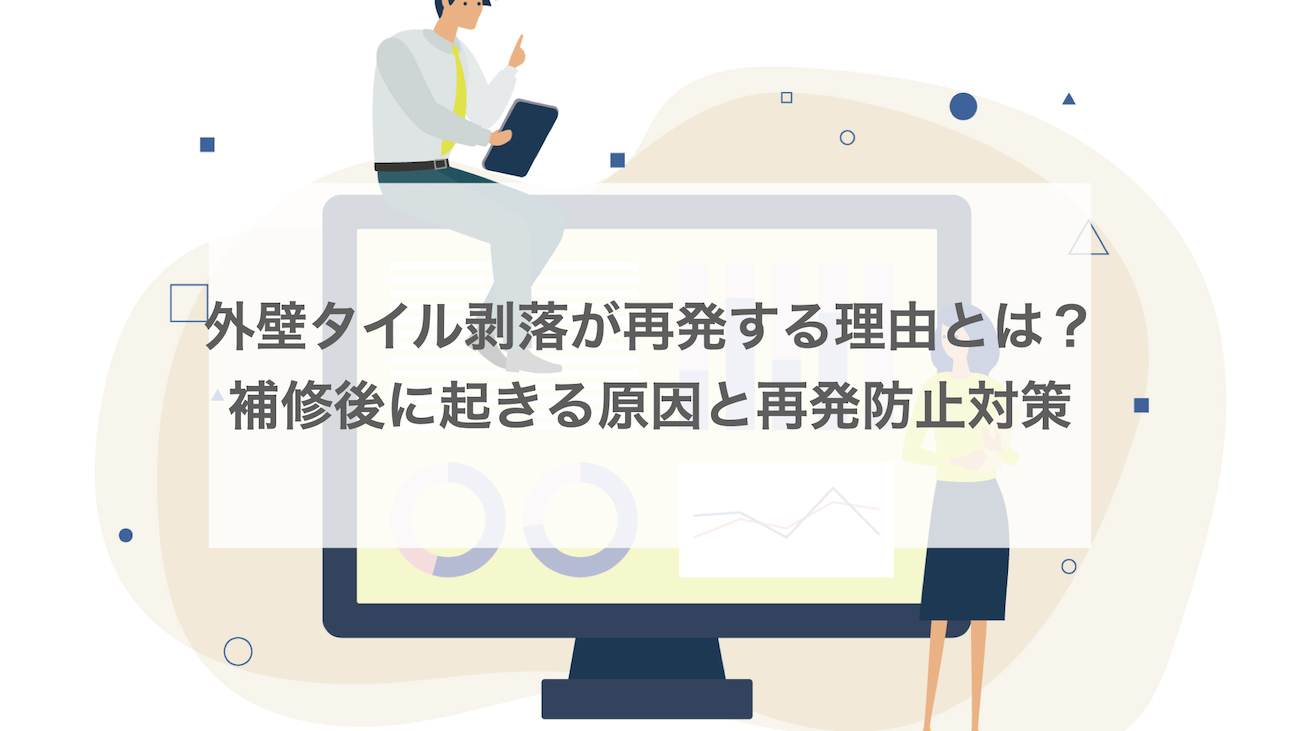
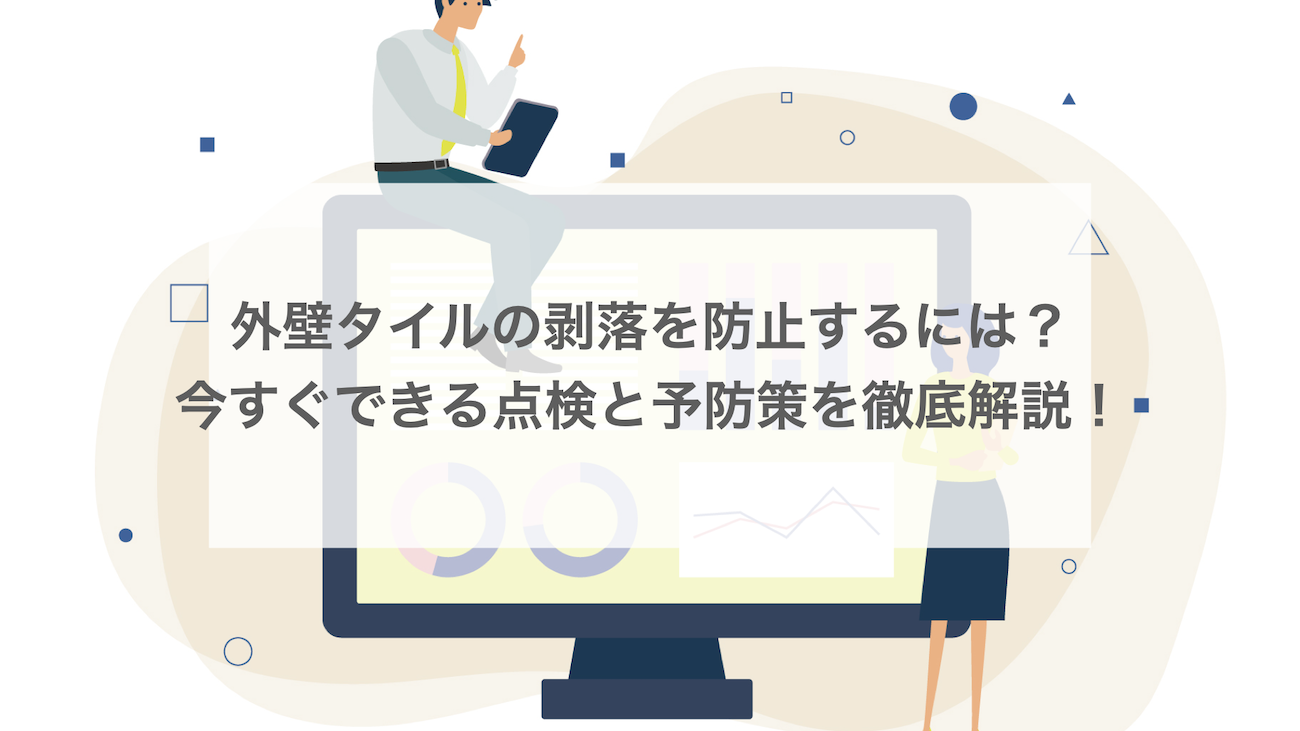
コメント