超速硬化ウレタン防水は立上りの納まりで差が出ると言われています。
屋上やベランダなどにある立上り部分の納まりに対してどのような施工をすればよいのか、その効果や耐久性などを知りたい人も多いのではないでしょうか。
- 超速硬化ウレタン防水工事でも立上り部の納まりが重要視されている理由について。
- 屋上やベランダなどにある立上り部でよく起こる不具合とその原因について。
- 超速硬化ウレタン防水施工時の下地処理とプライマー塗布のポイントについて。
- 超速硬化ウレタン防水でも立上りの納まりで差が出る理由と実例について。
- 超速硬化ウレタン防水工事の立上り部の納まりで注意すべきポイントについて。
- 超速硬化ウレタン防水は立上り部の納まりでどのような違いや差が出るのかに関するよくある質問まとめ。
超速硬化ウレタン防水は初期費用こそ高いものの非常に仕上がりも良く、耐久性や耐候性にも優れていると言われています。
屋上やベランダなどの立上り部の納まりを施工する際の基本と不具合対策はどのように考えればよいのか。
施工後のメンテナンスや防水効果を持続させるためにも立上り部の納まりに関する情報を紹介しますので、物件管理者や施工を検討している人は参考にしてください。
超速硬化ウレタン防水と立上りの納まりとは?
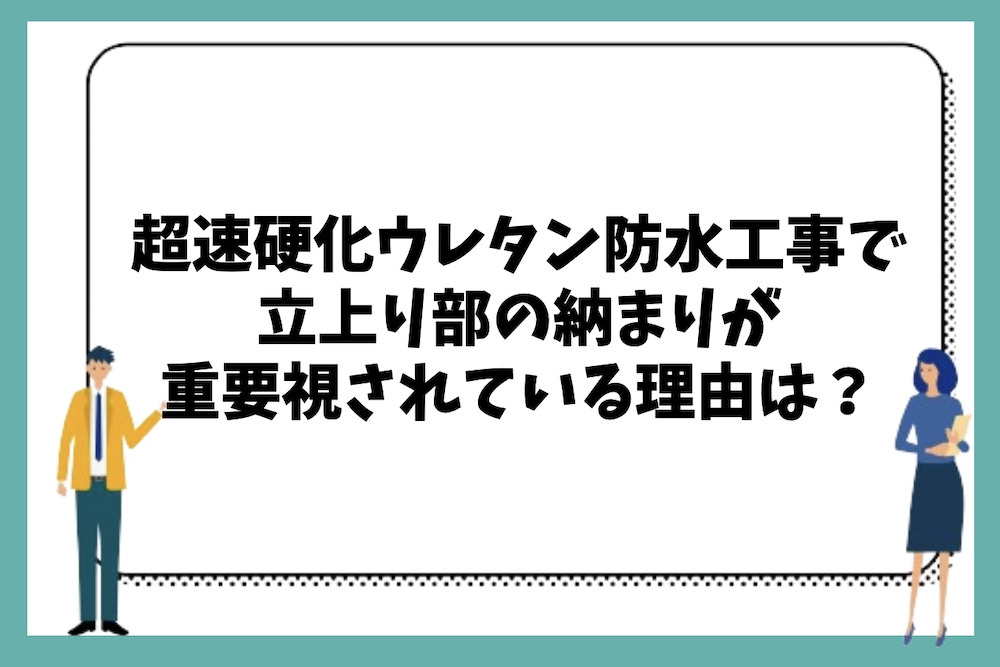
超速硬化ウレタン防水は、施工後わずか数秒〜数分で硬化するので、スピーディかつ高耐久な防水層を形成できることもあり、屋上やバルコニー、立体駐車場などで多くの現場で採用されるようになりました。
中でも立上り部の施工品質が仕上がりに大きく影響するため、正しい納まり設計と丁寧な施工が欠かせません。
まず最初に超速硬化ウレタン防水の特徴や立上りという言葉の意味、そしてなぜ立上りの納まりが重要視されるのかについて、初心者にもわかりやすく解説していきます。
超速硬化ウレタン防水の特徴と仕組みとは?
超速硬化ウレタン防水とは、スプレーガンで2液の材料を混合・吹付することで、数秒〜数分で硬化する防水材です。
従来のウレタン防水よりも工期が短く、凹凸面や複雑な形状にも対応しやすいため、屋上や立体駐車場のような広い面積や急勾配のある場所で多く使われています。
主な特徴は下記の通りです。
- 速乾性が高い:施工後すぐに歩行可能な場合もあり、工期短縮に貢献する。
- シームレスで継ぎ目がない:ローラーや刷毛と異なり、ムラや継ぎ目ができにくい。
- 複雑な形状にも対応:出隅・入隅・配管まわりなどの処理もスムーズ。
- 耐候性・耐久性が高い:紫外線や水分に強く、長期間性能を維持する。
このような特徴を活かすためにも、立上りや端部の納まりが丁寧であることが前提となります。
どれだけ優れた材料を使っても、納まりが悪いと漏水リスクが高まり、補修や再施工が必要になる場合があることは理解しておいてください。
立上りとは?建築用語としての意味は?
立上り(たちあがり)とは、防水層が床や水平面から垂直方向に立ち上がる部分のことを指します。
例えば、屋上の床から壁に向かって上がる部分や、手すりの基礎周辺などが該当すると理解しておいてください。
立上りの具体例は?
- 屋上床と壁の接合部
- パラペット(立ち上がった縁の壁)の内側
- サッシ周辺の立ち上がり
- 縦配管の根元部分
- 立体駐車場のスロープ接合部
このような箇所は水が溜まりやすく、また動きや収縮による応力が集中しやすいため、防水層の弱点になりやすい場所でもあります。
そのため、他の平面部以上に丁寧な下地処理や補強が求められていると理解しておきましょう。
立上り部の納まりが重要視される理由とは?
防水工事において立上りの納まりが重要視されるのは、漏水の原因となるリスクが最も高い箇所のひとつだからです。
平面部だけが完璧でも立上りに不備があれば、そこから水が侵入してしまいます。
納まり不良によって起こり得る不具合は?
- シートのめくれや浮き
- ウレタン層のひび割れや剥離
- 隙間からの雨水侵入
- サッシ周りの漏水による室内被害
立上り部は構造的にも複雑な形状が多いため、下記のような施工課題も発生しやすくなります。
立上り施工の難しさの要因は?
- 入隅・出隅が多く、材料が溜まりやすい
- 垂直面で材料が垂れやすい
- 配管やサッシなど障害物があると均一に施工しにくい
- 乾燥不良や厚み不足が発生しやすい
正しい納まり設計と経験豊富な職人による丁寧な作業が不可欠です。
特に超速硬化タイプは硬化が早い分、やり直しが効かないという特性があるため、一発勝負の精度が求められていると理解しておいてください。
立上り部の納まりは、防水の信頼性と耐久性を左右する重要なポイントです。
超速硬化ウレタン防水の性能を最大限に活かすためには、平面以上に立上り部に気を配り、丁寧な設計と施工を行う必要があることを理解して業者選びを行ってください。
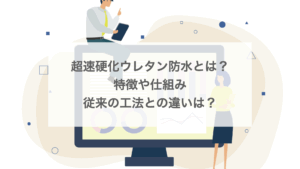
立上り部でよくある不具合とその原因は?
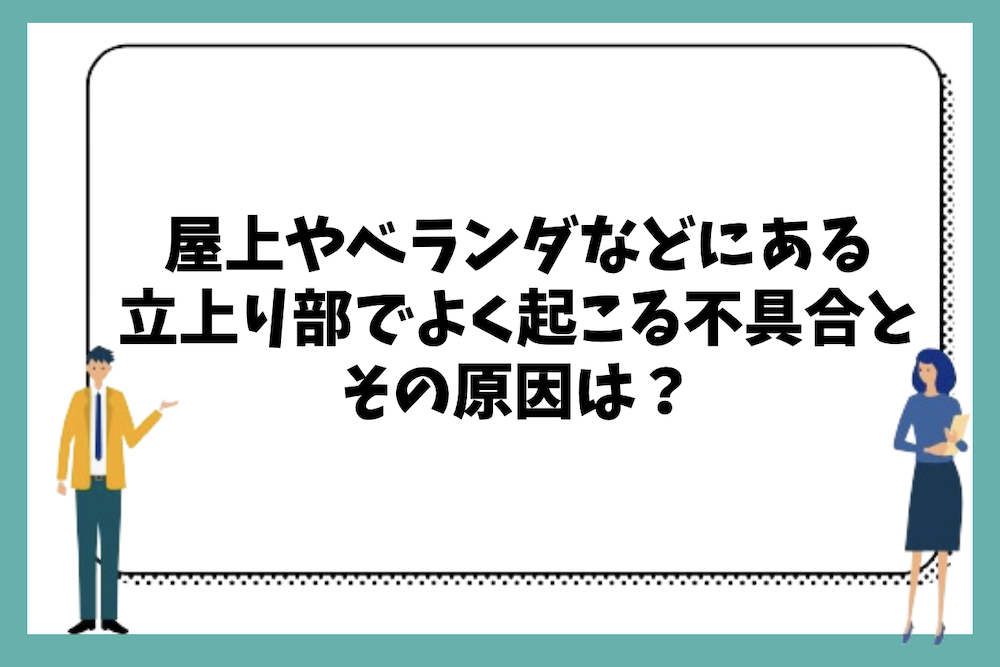
超速硬化ウレタン防水は、速乾性や高耐久性など多くのメリットを持つ防水工法ですが、特に立上り部は施工品質の差が不具合として表れやすい箇所です。
立上り部とは、床面から垂直に立ち上がる壁面との取り合い部分で、雨水の侵入リスクが高く、防水層が剥がれたりひび割れたりといった問題が多発しがちなポイントのひとつ。
現場でよく見られる立上り部の不具合とそれが起こる原因について初心者でも理解しやすいように、具体的な例と注意点も交えて紹介していきます。
ウレタンの塗膜剥離・浮き・亀裂
立上り部で特に多い不具合が、塗膜の剥離・浮き・ひび割れ(亀裂)です。
これらは施工不良や下地の処理不足など、さまざまな要因が重なることで発生します。
主な原因は?
- 下地の清掃不足:ホコリや油分、水分が残っていると、プライマーや防水材の密着性が低下。
- プライマーの塗りムラ:均一に塗布されていないと、浮きや剥がれが発生しやすい。
- 乾燥時間の不足:前工程が十分に乾いていない状態で次の層を施工すると、気泡や膨れの原因に。
- 立上り部の曲面施工:垂直面やコーナー部分は塗布が難しく、膜厚が不足することがある。
よくある症状は?
- 施工から数ヶ月〜1年以内に塗膜が浮いてくる
- 表面に微細なひび割れが現れ、雨水が浸入
- 塗膜が膨れてしまい、美観を損なう
基本的な対策は?
- 下地処理(高圧洗浄、プライマーの適正使用)を徹底
- 硬化時間・乾燥時間をしっかり守る
- 入隅部に補強布(クロス)を挿入して密着性を高める
シーリングや目地処理の不備
立上り部と床の接合部や構造躯体の目地などには、シーリング材での処理が欠かせません。
この処理が不十分な場合、防水層の破断や漏水のリスクが高まります。
よくあるミスは?
- 目地にバックアップ材を入れずに施工
- シーリング材の厚み不足
- プライマーの塗布忘れ
- 既存シーリングの撤去不十分
不具合例は?
- 施工後半年〜1年程度で目地から漏水が発生
- 防水層が動きに耐えられず亀裂が発生
- シーリングが痩せてしまい、隙間が空く
対策方法は?
- 目地幅や深さに応じたバックアップ材の使用
- シーリング材の2面接着を基本とする
- 乾燥後に再チェックし、必要があれば増し打ち処理を行う
ポイント
- シーリング処理は単なる防水補助ではなく、「動きに追従する緩衝材」としても重要な役割を持っています。
- 特に高架下や屋上などで温度差や振動の影響を受けやすい場所では、シーリングの質が防水全体の耐久性を左右します。
複雑な形状部位で起こりやすいトラブルは?
立上り部が出隅・入隅・配管まわり・手すり台座まわりなど複雑な形状をしていると、どうしても防水施工が難しくなります。
こうした場所でのトラブル例は?
- コーナー部分の膜厚不足で防水層が破断
- 配管まわりの納まりが悪く、水の浸入口になってしまう
- ジョイントや段差部の処理不良で漏水
特に注意すべき箇所は?
- 入隅(内側の角)・出隅(外側の角)
- 設備配管・支持金具などの貫通部
- 屋上のルーフドレン周辺
- 手すり脚部や点検口の立ち上がり周囲
トラブルを防ぐポイントは?
- 簡易図を作成し、施工前に納まりを設計
- 補強クロスやハットジョイナーなどで物理的補強を施す
- 必ず膜厚を測定し、基準値(2〜3mm)を下回らないよう確認
施工時の工夫は?
- スプレーガンやローラーの使い分けを徹底
- 硬化時間の速さを活かして「2回塗り」で膜厚を確保
- 一体化しづらい箇所は、先行塗布+本体施工で継ぎ目をなじませる
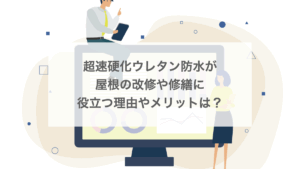
正しい納まりの基本:立上り部の施工手順は?
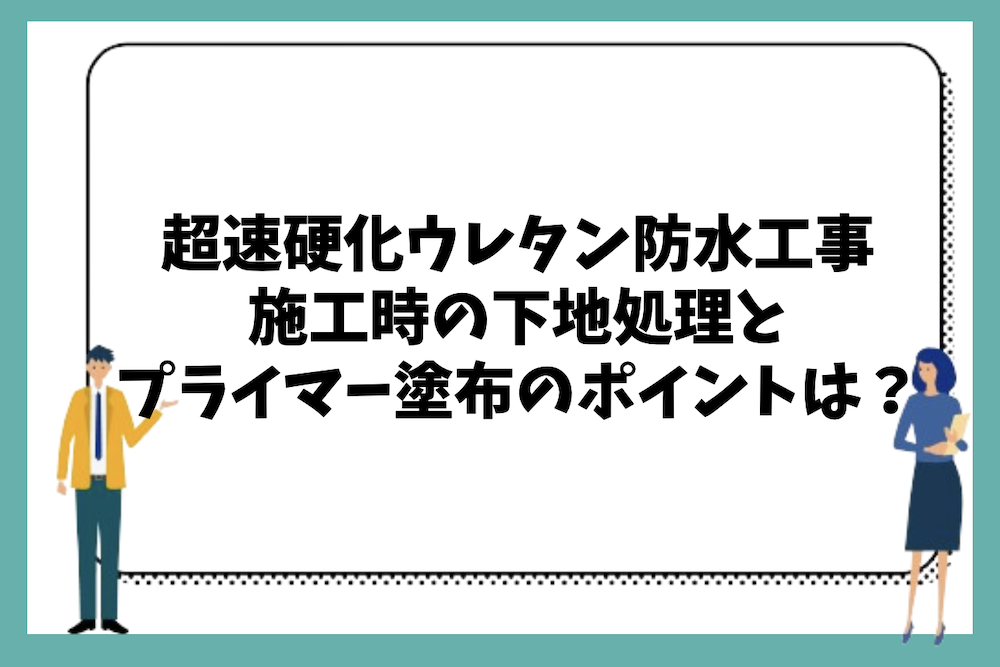
立上り部分の納まりは、防水性能に大きな影響を与える重要なポイントです。
特に超速硬化ウレタン防水では、施工スピードの速さゆえに工程ごとの丁寧な処理が求められていると理解しておいてください。
立上り部における正しい施工手順をわかりやすく説明していきます。
初めて防水工事に関わる方でも理解しやすいように、工程の流れや注意点、使用する材料や道具などの情報も含めて紹介していきますので、参考にしてください。
下地処理とプライマー塗布のポイントは?
立上り部の施工では、まず下地処理が最も重要です。
汚れやホコリ、油分などが残っていると防水層が密着せず、後々の浮きや剥がれの原因となります。
下地の種類(コンクリート、モルタル、金属など)に応じた処理が必要ですので、下記を参考にしてください。
- 表面の清掃:掃除機やブラシでホコリを除去
- 油分除去:シンナーやアルコールで拭き取り
- 凹凸の補修:クラックや段差を補修材で埋める
- 乾燥状態の確認:雨上がりは完全乾燥を待つ
下地処理が完了したら、プライマーを塗布します。
これはウレタンとの密着性を高めるために欠かせない工程です。
立上り部は垂直面なので、液だれに注意して、ローラーや刷毛で均一に塗ってください。
塗りムラがあるとその部分が弱点となり、漏水の原因となるでしょう。
メッシュシートや補強材の活用方法は?
立上り部は特に動きが出やすく、ひび割れや剥がれが起きやすい箇所です。
そこで、メッシュシートや補強布(クロス)を使用することで耐久性を格段に向上させることができます。
メッシュの主な役割は?
- ウレタンの厚み保持
- 動きのある箇所への追従
- 下地の不均一な力を分散
施工時は、プライマーを塗布した後に補強メッシュを立上り部全体または端部に貼り付け、軽く押さえて密着させます。
その後、ウレタンを塗布してシートを包み込むようにしてください。
特に入隅や出隅、段差部には重点的に補強することが望ましいでしょう。
ウレタン塗布時の厚み・乾燥時間の管理は?
超速硬化ウレタン防水は短時間で硬化するのが特徴ですが、厚みと乾燥時間の管理が非常に重要です。
立上り部では重力の影響で塗布が薄くなりやすいため、均一な厚みを確保する工夫が求められます。
- 1層目は薄く均一に塗布して、流れ落ちないように
- 2層目以降で規定厚み(1.5〜2.0mm程度)を目指す
- 完全硬化を待つ前に次の工程へ進むと不具合の原因に
- 施工後24時間以内の雨はNG
乾燥不十分で次の層を塗ると、内部でガスが発生して膨れや剥がれの原因となります。
温度や湿度によって乾燥時間が変わるため、現場の状況に応じた調整が必要です。
端部・入隅・出隅の処理方法は?
立上り部の「端部」「入隅」「出隅」は、最も雨水が侵入しやすく、トラブルが起きやすい部分です。
これらの箇所は特に丁寧な処理が求められます。
端部の処理は?
- 金物などでしっかり押さえる(端部押さえ金具)
- ウレタンの塗り残しに注意する
入隅の処理は?
- ハケで丁寧に塗布する
- 角がシャープすぎる場合はシーリングなどでR(丸み)をつける
出隅の処理は?
- ウレタンが垂れやすいので注意する
- メッシュを巻き込んで強度を高める
上記に加えて雨押えや立上り端部は金物とシーリングで最終仕上げするのが基本です。
防水層を長持ちさせるためには、これらのディテール処理が非常に大きな差を生みますので、絶対に手抜きをせずに行うようにしてください。
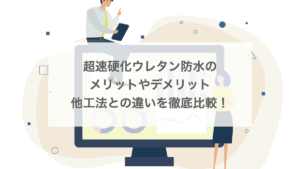
立上りの納まりで差が出る理由と実例比較
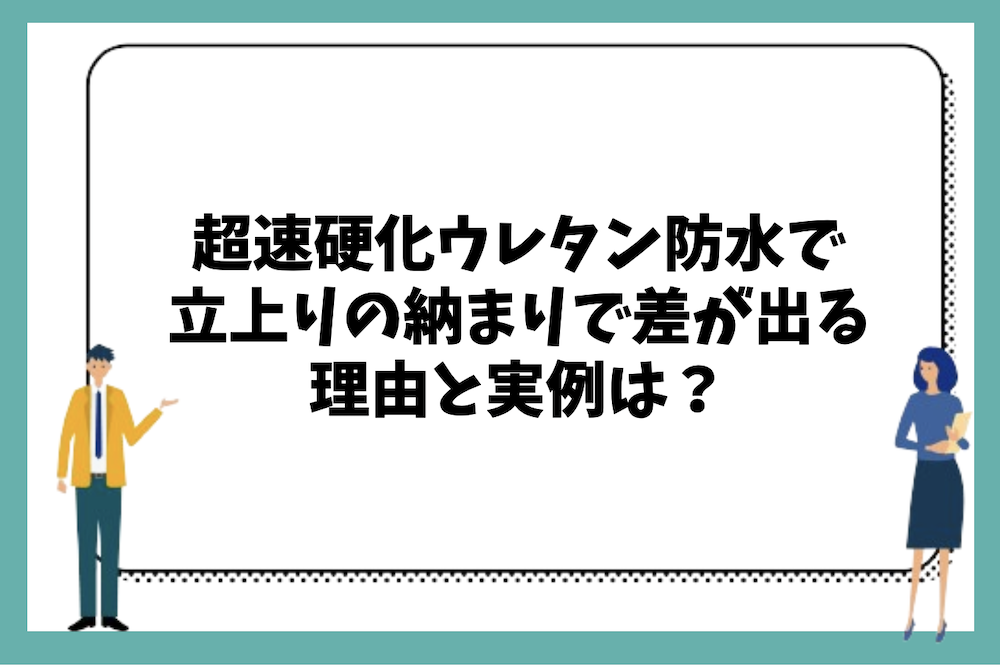
超速硬化ウレタン防水はスピードと耐久性に優れた工法ですが、特に立上り部の納まりが品質を左右する重要なポイントになります。
平場と異なり、立上り部は雨水の侵入リスクが高く、仕上がりの良し悪しがトラブルの有無に直結するということ。
納まりの良し悪しによって生じた実例と結果を比較して、正確な納まりがもたらす具体的なメリットや施工精度と長期耐久性との関係性について説明していきます。
納まりが悪いとどうなる?実例と結果
立上り部の納まりが不適切なまま施工されると、時間の経過とともに以下のような問題が発生します
- 雨水の侵入や漏水の発生
- 塗膜の浮きや膨れ
- クラック(ひび割れ)
- 接合部の剥離
例えば、あるビルでは立上りと平場の取り合い部分の下地が十分に清掃されておらず、ウレタンが密着せずに1年足らずで剥離が発生。
結果的に雨水が内部に侵入して、内装材の交換や漏水対策工事が必要になりました。
また別の例では目地シーリングの未施工により、立上りコーナーから水が浸入。
調査の結果、防水層自体に問題はなくても、納まりの甘さがトラブルの原因だと判明しました。
見た目では判断できない微細な納まりの乱れが、大きな補修工事や資産価値の低下につながることも。
施工時の丁寧さと確認作業を徹底することの重要性についてよくわかったと思います。
納まりを丁寧に行ったケースのメリットは?
立上り部の納まりを丁寧に仕上げた現場では、下記のようなメリットが得られます。
- 長期間にわたり防水効果を維持
- メンテナンスコストの削減
- 外観の美しさが長持ち
- クレームやトラブルの減少
例えば、公共施設の屋上改修工事では、立上り部に丁寧なプライマー塗布と補強布の重ね張りを行い、端部処理には二重塗りを採用。
その結果、10年以上経過しても一度も防水トラブルが発生していません。
施主からは、初期費用は少しかかったけどその後の維持費が安く済んでいると高評価を得ています。
また、マンションの共用廊下部分で、立上りと笠木の接合部を精密に納めたケースでは、施工から7年経過しても塗膜の劣化は最小限で住民からのクレームもゼロでした。
これらの事例は、立上り部の丁寧な納まりが防水性能だけでなく、管理コストや居住者満足度にも直結することを示しています。
施工精度と長期耐久性の関係性は?
立上り部の納まりの良し悪しは、そのまま施工精度を表しており、最終的な防水層の耐久性に大きな影響を与えます。
防水層の寿命を左右する主な要素について紹介しておくと、
- 下地とウレタンの密着度
- 塗膜厚の均一性
- 補強材の配置バランス
- コーナーや端部の処理精度
同じ材料・同じ工法を使っていても、納まりを適当に処理した現場ときちんと設計・施工された現場では、5年後や10年後の状態に歴然とした差が出ます。
特に立上り部は、雨水の跳ね返りや結露によるダメージが蓄積しやすく、施工精度が低ければすぐに劣化が始まり箇所です。
定期点検時にも納まりが良い現場では補修の必要が少なく、防水層全体の持ちが長くなる傾向があります。
逆に雑な納まりだと点検のたびに何らかの処置が必要になる可能性が高く、長期的なコストが増加してしまうでしょう。
立上り部の納まり精度は見過ごされがちですが、長期的な品質と費用に直結する非常に重要な要素のひとつだと理解しておいてください。
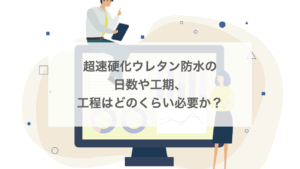
立上り部の納まりで注意すべきポイントは?
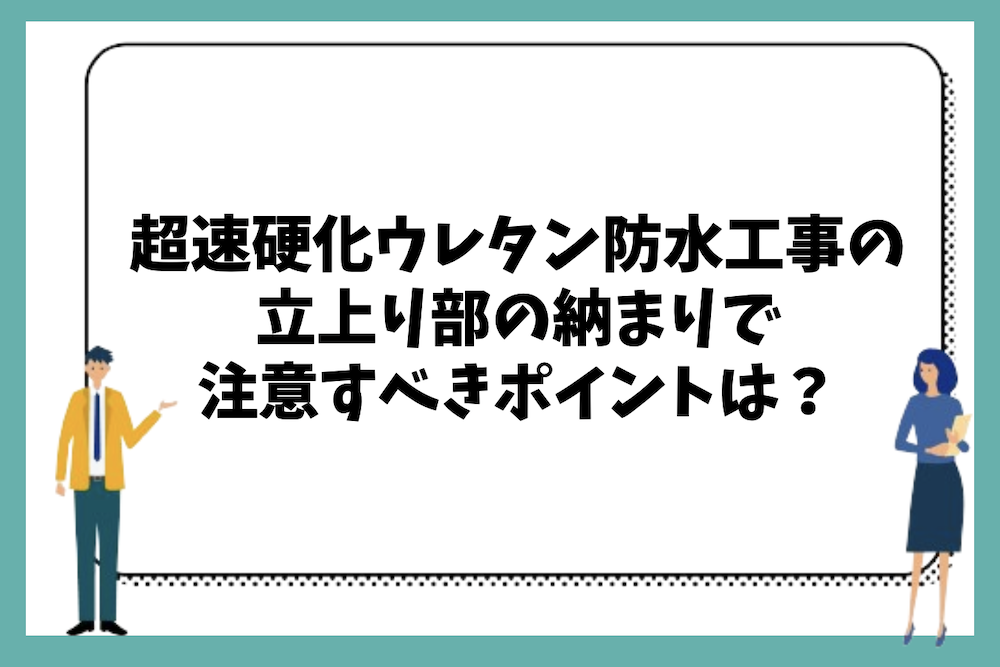
超速硬化ウレタン防水において、立上り部の納まりは防水性能や耐久性に直結する非常に重要なポイントです。
見た目の仕上がりだけでなく、漏水や剥離といった不具合を未然に防ぐためにも、設計・施工・維持管理の各段階で細かな配慮が求められているということ。
納まりに関して特に注意すべきポイントについて、設計・施工・維持管理の3つのフェーズに分けて説明していきます。
これらのポイントを正しく押さえておくことで、長寿命でトラブルの少ない防水層を実現することができますので、ぜひ参考にしてください。
設計段階で考慮すべき納まり条件とは?
設計段階から立上り部の納まりを意識することで、後のトラブルを大きく減らすことができます。
主な設計上の注意点は?
- 立上り高さの確保(150mm以上推奨):水跳ねや風雨に備えるため、躯体の立ち上がりは十分に取る
- 下地形状はシンプルにする:出隅や入隅が多すぎると納まりが複雑になり、施工不良の原因に
- 端部・開口部との取り合い:ドレン・手すり・配管などの取り合い部も、納まりに配慮した設計が必要
- 目地の処理を考慮する:建物の動きに追従できるよう、可動部の目地配置とシーリング材の選定
設計段階で施工性と防水性を両立した納まりを意識しておくことで、現場での迷いが減り、施工ミスの防止につながります。
現場での施工管理のチェックリストは?
図面通りに施工するだけでは、万全な防水ができるとは限りません。
現場での確認作業と細かな作業管理が納まりの精度を大きく左右します。
現場管理で特にチェックすべきポイントは?
- 下地の乾燥状態・清掃の徹底:水分・ホコリが残ると密着不良の原因になる
- プライマー塗布の有無と範囲:特に立上り部の端部に塗りムラがないかをチェック
- 補強布(メッシュ)の折り返しが足りているか:出隅や入隅など、動きが大きい箇所には補強必須
- 立上りの厚みと均一性:見た目でごまかされず、厚みゲージなどで実測確認
- 乾燥時間の確保と中塗り、上塗りの順守:指定された乾燥時間を守らないと接着不良が発生
チェックリストを用意して施工中に逐一確認することで、人的ミスを最小限に抑えることができるでしょう。
定期点検とメンテナンスで目指す長寿命化
立上り部は外的要因(紫外線・風雨・衝撃)を受けやすいため、施工後の定期点検と早期メンテナンスが欠かせません。
点検・メンテナンスのポイントは?
- 定期的な目視点検(半年~1年に1回):塗膜の変色・膨れ・ひび割れを確認
- シーリングの劣化チェック:立上りと平場の接合部や取り合い部のシールは特に注意
- トップコートの再塗布:紫外線劣化を防ぐため、5〜7年ごとの再塗布がおすすめ
- 部分的な補修の実施:ひびや剥がれは、早めに補修して拡大を防ぐ
防水層の不具合は放置すると大掛かりな修繕につながります。
特に立上り部は点検する度に重点的にチェックするようにしてください。
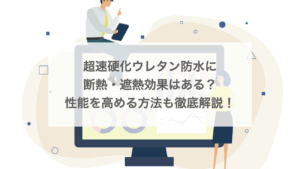
超速硬化ウレタン防水は立上り部の納まりの施工に関するよくある質問まとめ。
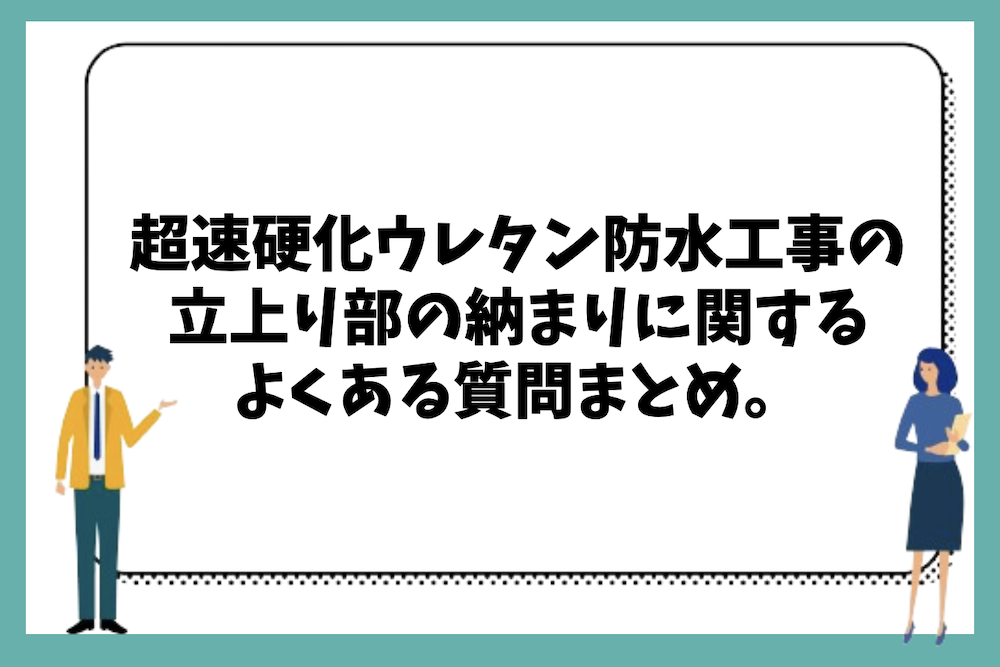
超速硬化ウレタン防水は、その速乾性と施工効率の高さから多くの建築現場で採用されていますが、特に立上り部の納まりは仕上がりの品質や耐久性に大きな影響を与える重要な要素です。
立上り部は防水層が垂直面に切り替わる箇所であり、処理が甘いと漏水や塗膜の剥離といった不具合が起こりやすいポイントのひとつ。
立上り部における納まりの重要性や施工手順、トラブル例と対策について、よくある質問としてまとめて紹介しますので、施工時や導入時の参考にしてください。
超速硬化ウレタン防水において、立上りの納まりが特に重要視されるのはなぜですか?
立上り部は平場と違って垂直面であり、防水層の連続性を保つうえで最も弱点になりやすい箇所です。雨水が集中しやすく、施工時の不備があるとすぐに剥離や浮き、漏水の原因となります。また建物の揺れや熱伸縮などにより動きが出やすい部位でもあるため、シーリングや補強材の使い方次第で耐久性に大きな差が生まれます。納まりが不適切だと短期間で劣化が進み、再施工やクレームにつながるケースも多いため、初期施工の品質管理が極めて重要だということです。
立上り部でよく発生するトラブルにはどのようなものがありますか?
立上り部で発生する主なトラブルは、塗膜の剥離、膨れ、亀裂、シーリングの劣化などです。特に下地処理やプライマーの塗りムラがあると密着不良を引き起こして、時間が経つと防水層が浮いたり破れたりします。また目地やクラックの処理不足も雨水の侵入経路になります。さらに出隅・入隅など複雑な形状部分では塗膜厚が不足しやすく、不具合の起点になることも。すべては施工精度と納まり処理の適切さが関わっています。
設計段階で考慮しておくべき納まりのポイントは?
設計段階では下記ポイントを押さえておく必要があります。①立上りの高さを300mm以上確保する②入隅・出隅が極端に狭くならないよう設計る③シーリング材や伸縮目地との取り合いを事前に想定る④補強部材の納まりスペースを確保る⑤設備配管や貫通部の周囲の処理計画を立てる。これらを事前に計画しておくことで、現場での無理な納まり処理を防ぎ、仕上がり品質を安定させることができるでしょう。
納まりの良し悪しは長期耐久性にどのように関わってきますか?
納まりが正確で施工精度が高いほど、外部環境からの影響を受けにくくなり、防水層の耐久性は飛躍的に向上します。逆に雑な納まりでは紫外線や雨水によるダメージを直撃で受けやすく、数年で不具合が出る可能性も高くなります。結果として、再施工の頻度が上がり、ライフサイクルコストも増大しますので、長く使える建物を目指すには、初期の納まりこそが最も重要な投資だということを理解しておいてください。
立上り部の納まりに失敗した場合のリスクとは?
立上り部の納まりに問題があると、防水層のめくれ・浮き・剥離が起こりやすくなり、結果として漏水や躯体の劣化につながります。特に施工初期は異常が見られなくても、数ヶ月~数年後に症状が現れることが多く、補修や再施工のコストが発生します。最悪の場合は、内装や電気設備の損傷にもつながり、大きなトラブルとなることもあるため、初期施工の精度が非常に重要だということを理解しておきましょう。
超速硬化ウレタン防水の立上りで推奨される補強材とは?
立上り部では、ウレタンだけでは不十分なケースもあるため、メッシュシートやガラスクロスなどの補強材の使用が推奨されます。これにより塗膜の強度が増して、ひび割れや剥がれのリスクを抑えることができます。特に入隅や出隅、段差部には、補強材をあらかじめ挿入することで応力集中を緩和し、長期的な耐久性を高める効果を期待することができるでしょう。
立上りと接する既存建材への影響はあるのか?
超速硬化ウレタン防水は、施工時に高温になることは少ないため、通常の建材に大きな熱影響を与えることはありません。しかしアルミサッシやガラス、金属部分など接着が難しい素材との取り合いでは、プライマー選定やシーリング処理が非常に重要です。また既存の塗膜や仕上げ材がある場合は、それらを適切に撤去・処理したうえでの施工するようにしてください。
ウレタン防水とシート防水における立上り納まりの違いは?
ウレタン防水は液状のため、立上りや複雑な形状にも連続的に施工できる点がメリットです。その一方で、シート防水では立上り部に継ぎ目やジョイントが生じやすく、処理が甘いと漏水の原因になります。形状が複雑な場合や段差が多い部位にはウレタン防水が適しているといえます。ただ施工技術に差が出やすいため、職人の腕が問われる点も考慮した業者選びが重要だということも忘れないでください。
定期点検時に立上り納まりの不良を見分けるポイントは?
定期点検時には、塗膜の浮きや剥がれ、ひび割れ、色ムラ、シーリングの劣化などを重点的にチェックしてください。特に端部や接合部、入隅・出隅は不具合が起こりやすい箇所ですので、触ってみて弾力がなかったり、軽く押すとペコペコするような感触があれば、内部に空気が入り込んでいる可能性があります。早期発見が劣化拡大を防ぐ鍵となりますので、施工後の定期点検は必ず実施するようにしてください。
納まりの悪い立上り部は補修することができますか?
納まり不良があっても状況に応じて補修は可能です。小さな剥がれやひび割れであれば、部分的な再塗布やシーリング補修で対応できます。ただ劣化が進行している場合や接着不良が広範囲に及ぶ場合は、既存防水層の撤去と再施工が必要になることも。劣化の進行度によって工法や材料を選定する必要があるため、専門業者による診断が重要ですので、施工業者と連絡を取りながら補修方法について検討してください。
立上り部の下地がコンクリートと鉄板で異なる場合、防水の納まりはどう対応すべきですか?
異なる下地素材が混在する場合、それぞれに適した下地処理とプライマーの選定が必須です。例えば、コンクリート部には水分を含んだ下地に強いエポキシ系プライマー、鉄板部には防錆性の高いプライマーを使用するなど、素材ごとに適切な処理を行ってください。また異種接合部には補強メッシュや目地処理を挿入して、動きの違いによるクラック発生を防止します。このように納まりの調整を的確に行うことで、複合下地でも高い防水性を確保することができるでしょう。
立上りの角が鋭角すぎる場合、防水材はどう納めればよいですか?
鋭角な入隅や出隅は塗膜が薄くなりやすく、不具合の原因になります。まず最初に角を面取りして、R(アール)加工することで塗布しやすい形状に整えます。さらに補強材(メッシュ)を使って角を保護し、塗膜の厚みが確保できるように施工します。鋭角のままでは均一な膜厚が得られず、防水層が脆弱になりますので、角の処理は丁寧に行うようにしてください。
納まり不良が原因の漏水は保証対象になりますか?
保証対象になるかどうかは契約内容や施工会社の保証制度によりますが、多くの場合、明らかな施工ミスや納まり不良による漏水は保証対象とされます。ただ経年劣化や定期点検を怠ったことによる劣化が原因の場合は、保証対象外となることもあります。保証を受けるためには、施工記録や点検記録をしっかり保管して、施工基準に従って納められていたことが重要だということも忘れないでください。
外壁との取り合い部の納まりで注意すべき点は?
外壁との取り合い部は異なる素材や構造が交わる場所であり、漏水リスクが高まるため注意が必要です。主なポイントは次の通りです。シーリング材を二重構造にする・立上り防水を外壁の防水層と十分に重ねる・補強メッシュを入れて層間の剥離を防ぐ。これらを徹底することで、水の侵入を防いで長期的な耐久性を確保することができるでしょう。
窓廻りやパラペット天端など立上りが短い場合の納まりは?
立上り高さが十分に確保できない箇所では、逆流や毛細管現象による水の侵入リスクが高まります。こうした箇所では、下記対策が有効です。立上りを最低でも150mm確保するよう設計変更を検討する・金属水切りや防水シートを併用して二重防水とする・端部にはシーリング材を厚く施して、水の進入経路を完全に遮断する。高さ不足は設計変更が難しいケースもあるため、複合的な工夫が必要ですので形状的にややこしい箇所がある場合は、施工実績の豊富な業者を選ぶようにしてください。
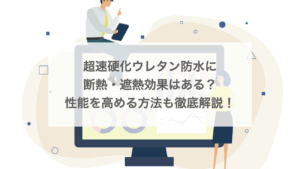
外壁の劣化状態の確認や修繕工事費用の無料見積もりはフェアリノベーション株式会社にお任せください。
マンションやアパートの外壁診断やリフォームに関することであれば、どのような相談でもお受けすることができます。
フェアリノベーション株式会社の外壁診断のおすすめポイント!
- 外壁診断のお見積もりは無料です。
- 訪問なしでお見積もりが可能です。
- 親切丁寧な対応が評判です。
- 疑問点は何度でも相談できます。
将来的な大規模修繕工事や外壁調査を検討されている方でも良いので、現状確認の為にもまずはお気軽にご連絡ください。

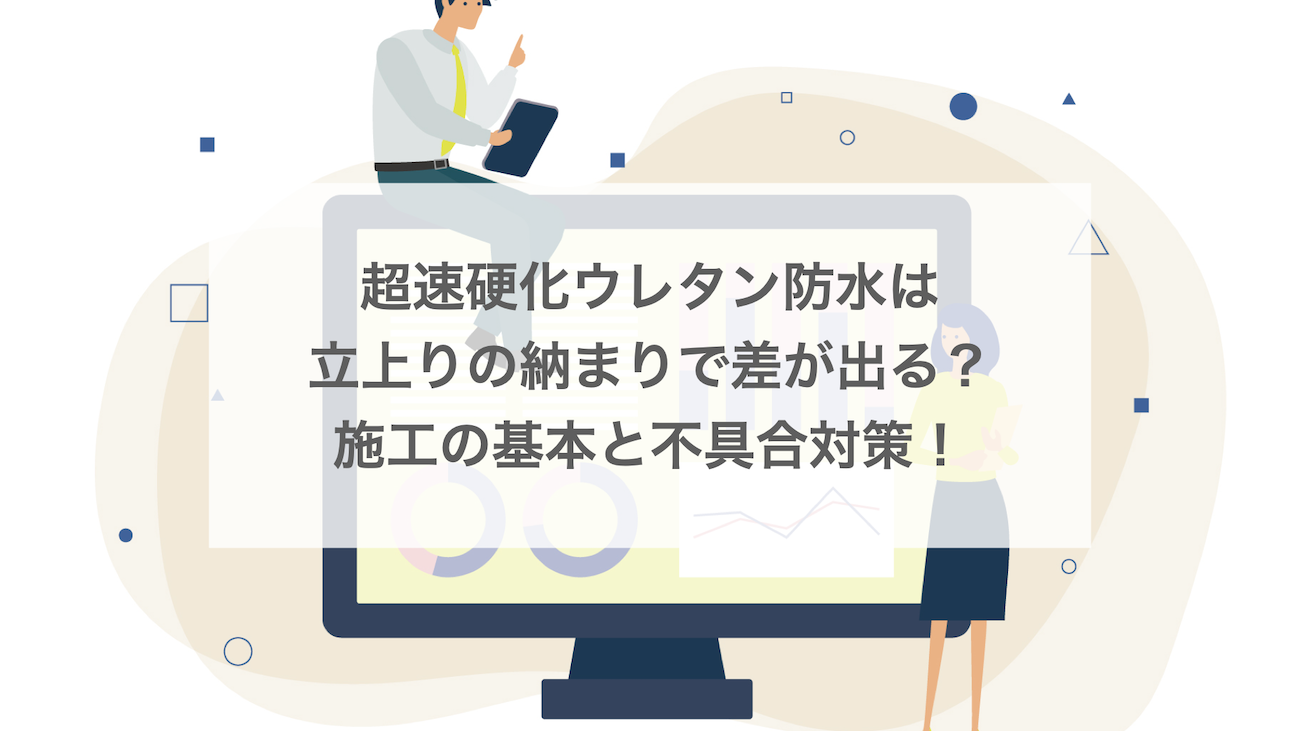
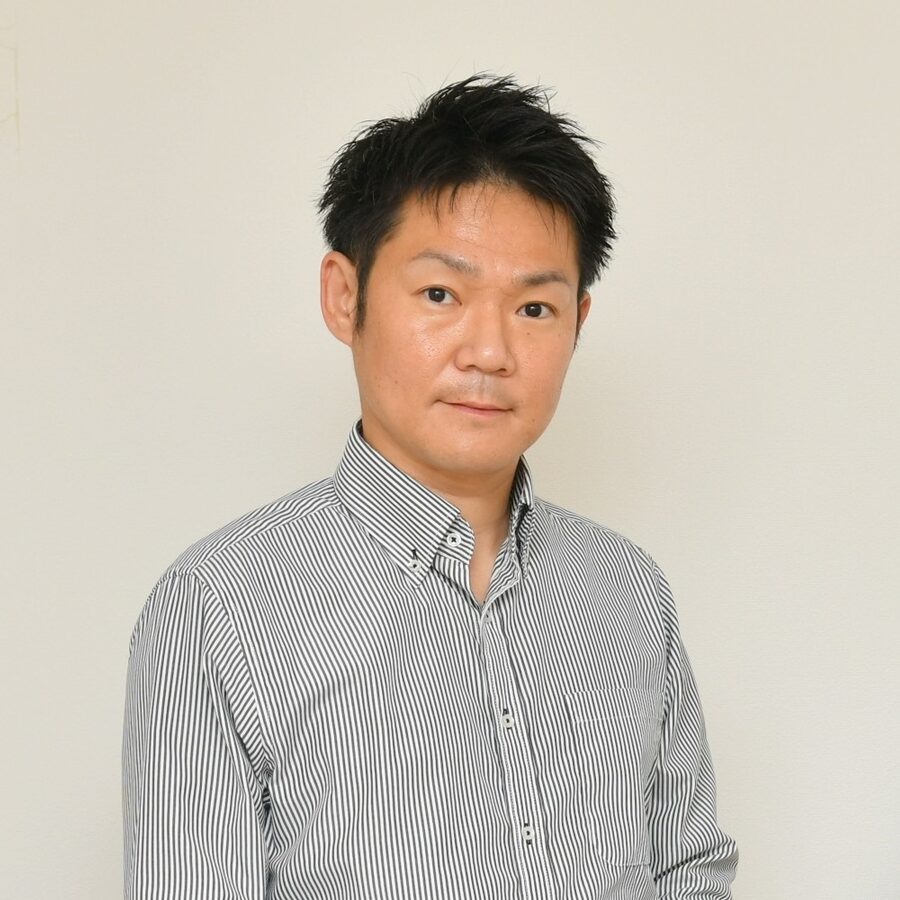
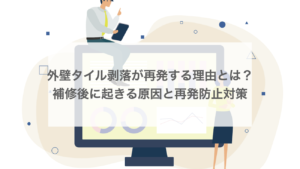
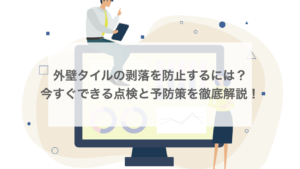
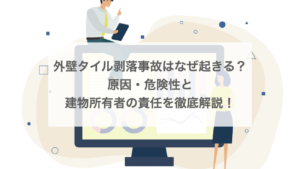
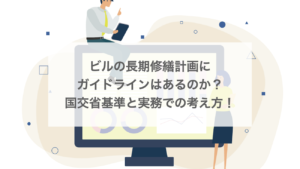
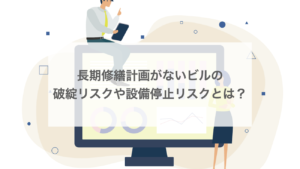
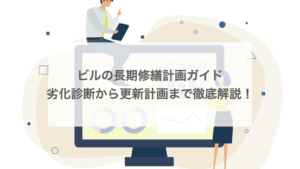
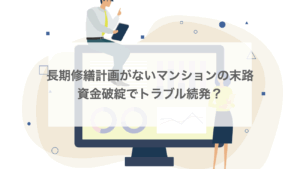
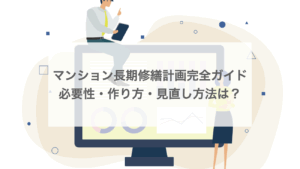
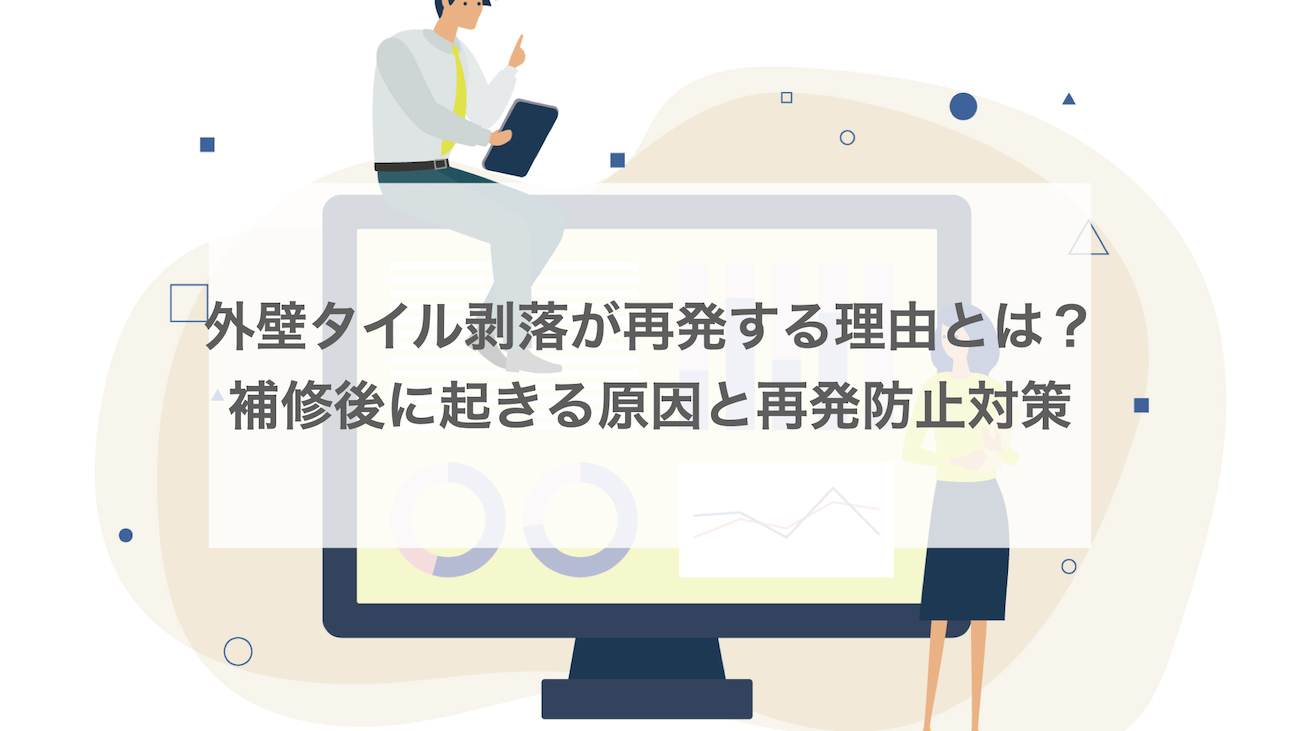
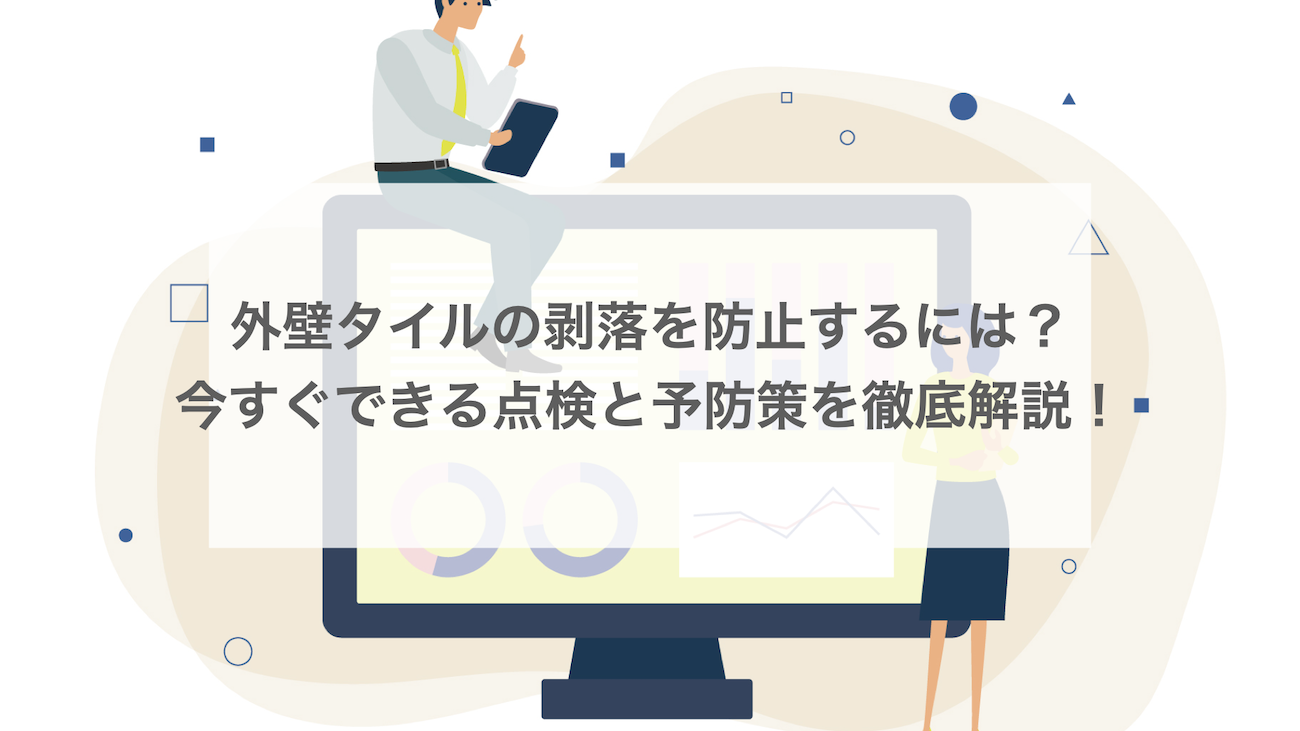
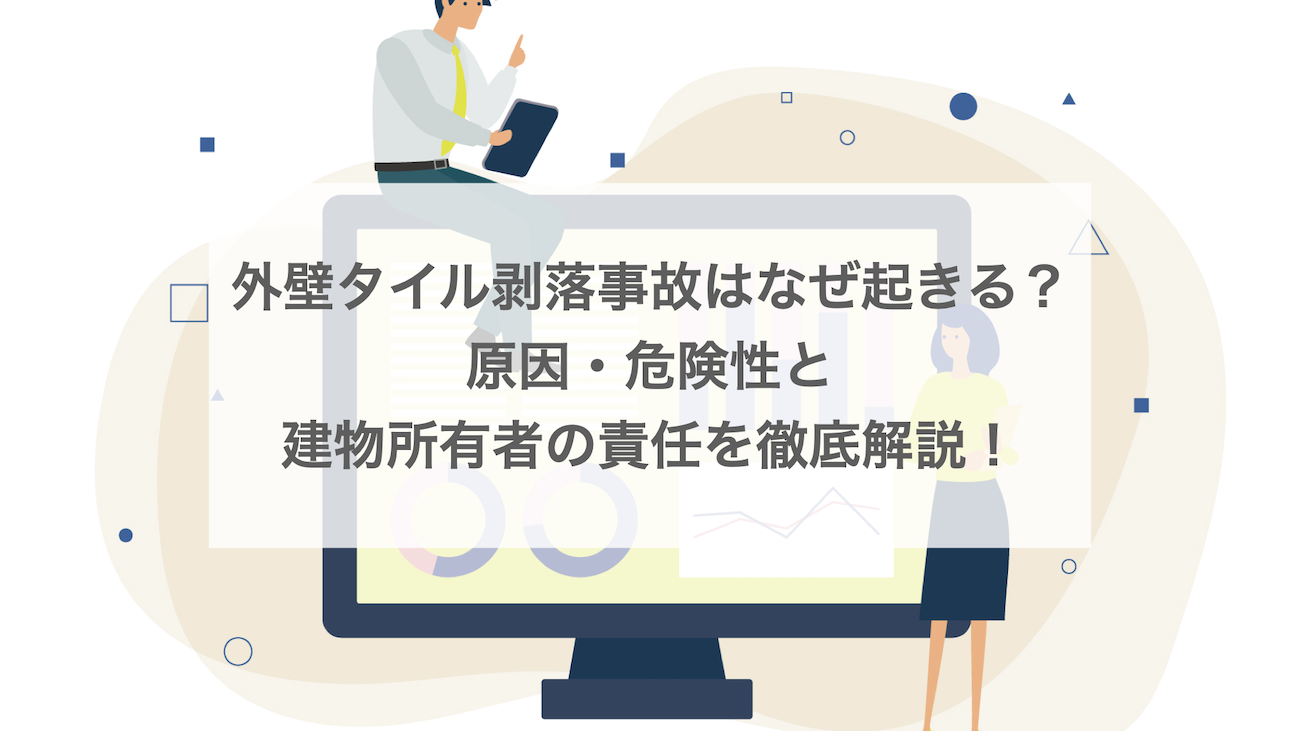
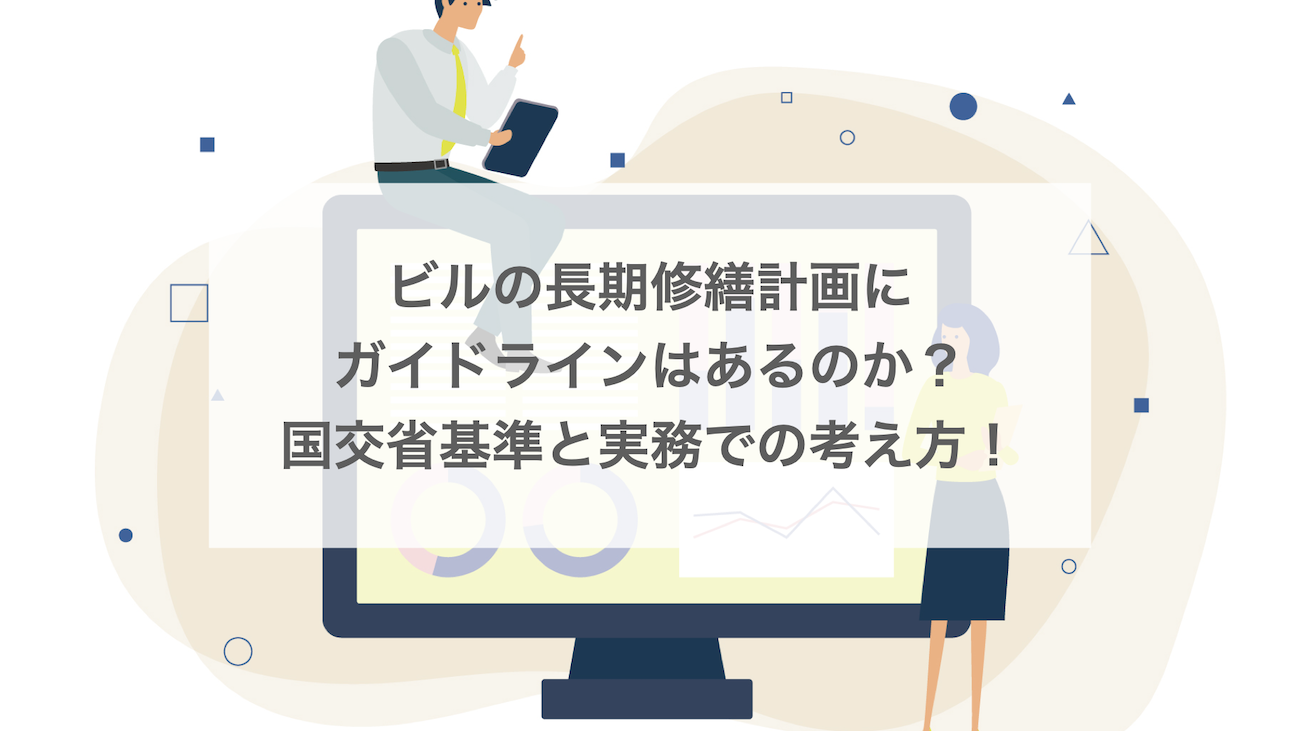

コメント