超速硬化ウレタン防水とはどのような特徴や仕組みがある防水工事の工法のことなのか。
従来の工法との違いも含めて、ここ数年で人気が高く評判となっている超速硬化ウレタン防水に関する基本的な情報をまとめて紹介します。
- 超速硬化ウレタン防水とはどのような特徴がある防水工事の工法のことなのかについて。
- 超速硬化ウレタン防水とはどのような仕組みで行われる防水工事の工法のことなのかについて。
- 超速硬化ウレタン防水工事をすることで得られるメリットやデメリットは何があるのかについて。
- 超速硬化ウレタン防水工事と従来の工法を比較した場合、費用やメンテナンス頻度にはどのような違いがあるのかについて。
- 超速硬化ウレタン防水工事が適している場所やケースにはどのようなものがあるのかについて。
- 超速硬化ウレタン防水工事の特徴や仕組み、従来の工法との違いに関するよくある質問まとめ。
以前からあったウレタン防水工事の進化系なので、超速硬化ウレタン防水が優れていることは間違いありません。
ただどのような点で優れているのかそのメリットやデメリットも含めて、基本的な情報を知らないとその効果を十分に享受できないことも。
この記事では超速硬化ウレタン防水工法に関する基本的な情報を踏まえながら、その特徴や従来の工法との違いについて詳しく紹介していきますので、まずはどんな防水工事か知りたい人は参考にしてください。
超速硬化ウレタン防水とは、どのような特徴がある工法なのか?
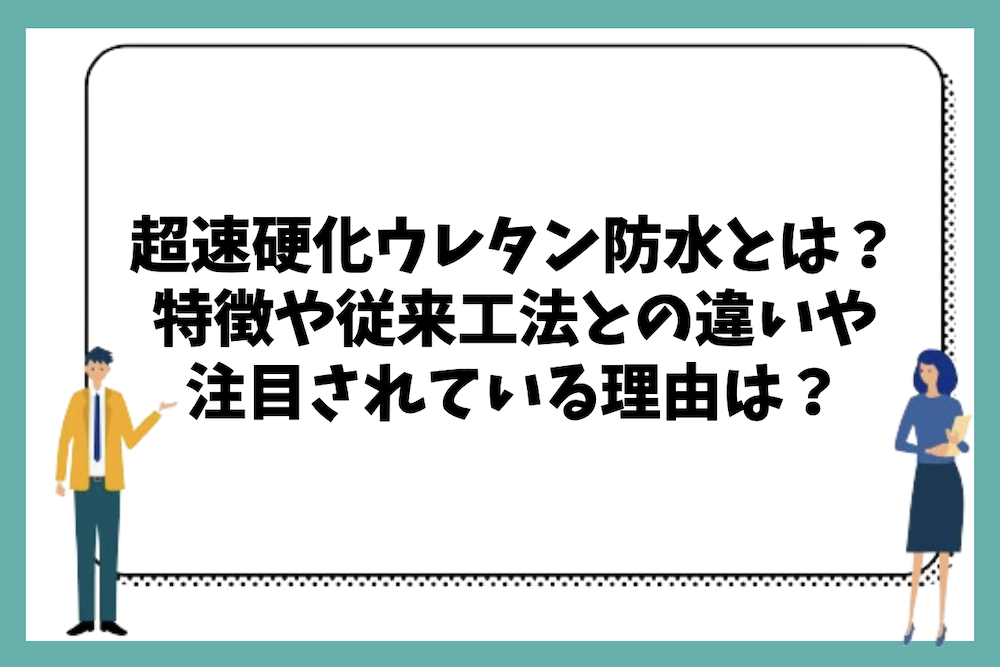
近年、ビルやマンション、商業施設などの防水工事の際に超速硬化ウレタン防水という工法が注目されているのを知っていますか。
液体状の特殊なウレタン樹脂をスプレーで吹き付けて、数秒から数分で硬化させることができる非常にスピーディーな防水工法のこと。
従来の手塗りによる防水工事に比べて工期が短いだけではなく、継ぎ目のない美しい仕上がりになるため、多くの現場で採用が進んでいます。
ここでは超速硬化ウレタン防水とは何か、その特徴や従来工法との違いなどの情報を初心者にもわかりやすく解説していきますので、基本情報を知りたい人は参考にしてください。
超速硬化ウレタン防水の定義と読み方は?
超速硬化ウレタン防水(ちょうそくこうかうれたんぼうすい)とは、その名のとおり、非常に速く固まるウレタン樹脂を使った防水工事のことです。
この工法では、特殊なスプレー機械を使うことで2種類の液体(主剤と硬化剤)を現場で混合しながら、建物の屋上や床面などに直接吹き付けて施工することができます。
ポイントは超速硬化という言葉が示すスピード感です。
- スプレー噴射後、わずか数秒〜数分で硬化が開始始まります。
- 乾燥を待たずにその日のうちに次の作業に進むことができます。
- 気温や湿度に左右されにくく、工期短縮に大きく貢献します。
超速硬化ウレタン防水工法の防水材として使われるウレタン樹脂は柔軟性と密着性が高く、防水性に優れた材料です。
吹き付け+超速硬化させることによってさらに施工性とスピードを高めたのが、この工法の最大の特徴だということをここでは覚えておいてください。
一般的なウレタン防水と超速硬化ウレタン防水工法との違いは?
超速硬化ウレタン防水とよく比較されるのが、従来から広く使われている手塗りウレタン防水です。
どちらもウレタン樹脂を使うという部分は共通していますが、施工方法と性能にいくつか大きな違いがありますので、比較した情報を一覧表で紹介すると、
| 比較項目 | 超速硬化ウレタン防水 | 一般的なウレタン防水 |
| 施工方法 | スプレーによる吹付け | ローラーやコテによる手塗り |
| 硬化時間 | 数秒〜数分で硬化 | 1層ごとに8〜24時間乾燥が必要 |
| 工期 | 1〜2日で完了も可能 | 3〜7日かかることが多い |
| 仕上がり | 継ぎ目のない均一な膜 | ムラや段差が出やすい場合がある |
| 複雑な形状への対応 | スプレーで細部も一体施工可能 | 時間と手間がかかる |
施工スピードと仕上がりの美しさ、対応力の高さで超速硬化型は優位性があるということ。
その一方で、手塗りタイプの方が小規模での施工やコスト調整に柔軟という面もありますので、状況に合わせて選ぶというのがおすすめです。
スプレー式で超速乾する超速硬化ウレタン防水工法の特徴とは?
超速硬化ウレタン防水の最大の特徴は、スプレーによる超速乾式の施工ができる部分で、主な特徴を簡単に紹介しておくと、
- 専用スプレー機で均一に吹付け:材料は2液混合型(A液:主剤/B液:硬化剤)で、吹付けと同時に化学反応が起こる。
- 吹き付け後すぐに硬化が始まる:5〜10秒でゲル化して、5分以内に歩行可能になる場合もある。
- 1日で全工程を完了できる場合もある:乾燥待ちがないため、天候や気温に左右されにくい特徴がある。
- 継ぎ目のないシームレスな仕上がり:施工面が一体化され、水の侵入経路を作らないなど効果が高い。
段差や凹凸、配管のあるような複雑な形状の場所でも隙間なく施工できるのが大きなメリットのひとつ。
これによって屋上やバルコニー、タンクの周辺など様々な環境に柔軟に対応することができます。
超速硬化ウレタン防水はなぜ注目されているのか?近年の需要背景にあるものは?
ここ数年で超速硬化ウレタン防水が急速に注目されるようになった背景として、下記のような状況が考えられます。
- 建物の老朽化と防水ニーズの増加:多くのマンションや商業施設が築20〜30年を超え、防水層の再施工が必要な時期を迎えており、工期が短く品質が安定する工法として注目されています。
- 短工期ニーズの拡大:病院や学校、商業施設などでは短い休業期間中に工事を終わらせたいという声が増えており、超速硬化タイプは1〜2日で施工が完了するため日数制限のある現場にぴったりです。
- 品質と施工の安定性:吹き付けによって職人の熟練度に左右されにくい均一な仕上がりが得られるだけではなく、専用機械による施工で品質が一定化するために管理のしやすさも評価されています。
- SDGs・環境配慮への対応:近年では、無溶剤・低臭気の材料も普及して、作業員や周辺環境に配慮した施工が可能になったことで、環境負荷を抑える工法として、公共工事でも採用が増えています。
超速硬化ウレタン防水とは、数秒〜数分で硬化するスプレー式の防水工法のことで、一般的な手塗りウレタンよりもスピード・美観・対応力で優れている特徴があります。
近年の老朽化対応や短工期需要、施工安定性のニーズにマッチして注目されていますので、次回の大規模修繕工事の際に採用する工法として検討するのもありかもしれません。
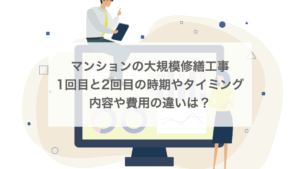
超速硬化ウレタン防水の仕組みと基本的な施工方法は?
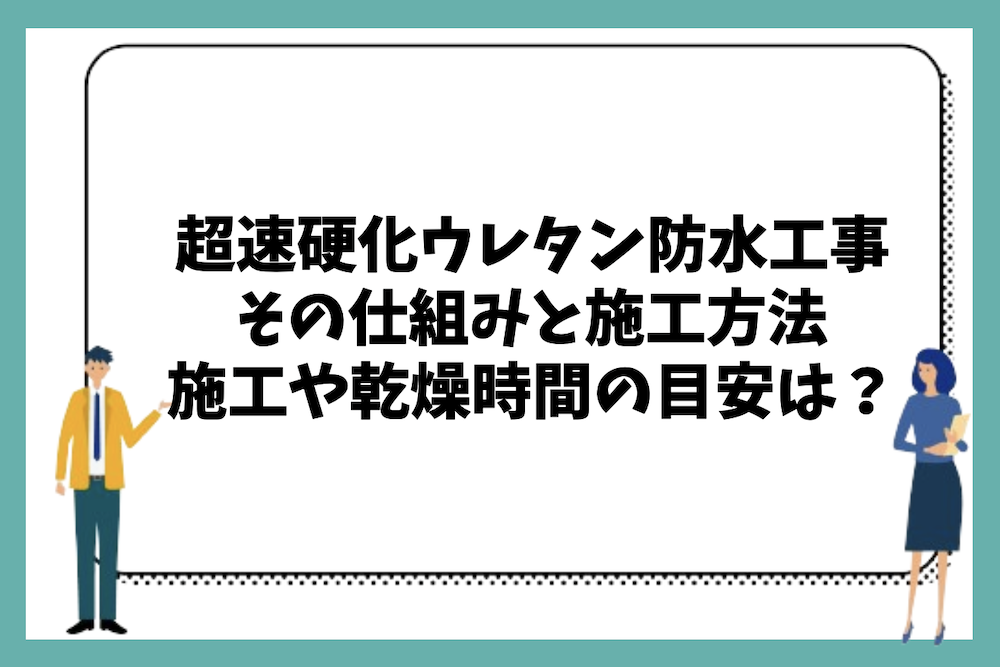
超速硬化ウレタン防水は従来の手塗り工法とは大きく異なり、専用スプレー機を使用してウレタン樹脂を施工面に直接吹き付けることで防水効果を発揮させる最新の防水技術です。
この工法の特徴は速さと密着性で、わずか数分で硬化することで工期の大幅短縮が可能になることが挙げられます。
超速硬化ウレタン防水工法がどのような仕組みで成り立っているのか、実際の施工ステップと施工時間や注意点などをわかりやすく解説していきますので、参考にしてください。
超速硬化のメカニズムである2液混合型とは?
超速硬化ウレタン防水は、2液混合型のウレタン樹脂を使います。
主剤(A液)と硬化剤(B液)の2種類の液体を専用のスプレー機械で混ぜながら吹き付ける工法のこと。
超速硬化メカニズムのポイントは?
ウレタン主成分(樹脂)と反応性硬化剤(イソシアネートなど)が混ざることで、すぐに化学反応が起こってすぐに硬化が始まる仕組みになっている部分です。
なぜ超速硬化なのか?
通常のウレタン防水工法では、1層ごとに数時間〜半日かけて乾かす必要がありましたので、かなり時間と手間がかかっていた部分がありました。
超速硬化型では、吹き付けた直後から数秒〜数分でゲル化(柔らかいゼリー状に)し、5分程度で歩行できる状態にまで固まります。
これによって作業時間が大幅に短縮され、施工効率が大きく向上しますので、それが天候や工期にシビアな現場で高い評価を得る結果となっているということ。
実際の施工ステップ(下地処理〜吹付〜トップコート)の流れは?
超速硬化ウレタン防水の施工は、下記のようなステップで進みます。
見た目の派手さとは裏腹に下地処理などの地味な工程が品質を左右しますので、防水工事である以上、基本的な部分は抑えておく必要があるという部分に違いはありません。
ステップ1:下地処理
施工前にコンクリート面や既存防水層の汚れ・油分・浮き・割れなどをしっかり除去します。
不良部分は補修して防水材がしっかり密着する状態に整えることが非常に重要なポイントです。
ステップ2:プライマー塗布
プライマーとは、下地と防水材をしっかり接着させるための接着剤のような役割を持つ液体のことです。
使用するウレタン材に適したプライマーを、均一に塗り残しなく塗布する必要があります。
ステップ3:ウレタン吹き付け(主材)
専用のスプレー機で、A液とB液を同時に混合しながら吹き付けます。
一度の吹付けで1.5mm〜3.0mm程度の膜厚の確保ができるだけではなく、段差や突起物があっても継ぎ目なく施工することができます。
ステップ4:トップコート塗布
最後に紫外線や摩耗から防水層を守るために必要なトップコートを上から塗布します。
トップコートには遮熱機能付きや高耐久型などもありますので、用途に応じて使い分けてください。
施工時間や乾燥時間の目安は?
超速硬化ウレタン防水の最大の魅力は施工スピードの速さですので、実際の施工時間目安を紹介すると、
各工程の時間目安は?
- 下地処理・プライマー塗布:1日(状況により半日)
- 吹付け施工(主材):数時間〜半日(広さによる)
- トップコート塗布〜乾燥:約1〜2時間(素材による)
工期全体の目安は?
- 30㎡程度の小規模屋上なら1日で完了させることも可能。
- 100㎡を超える広さでも2〜3日で完了することが多い。
吹付け後すぐに歩行可能な状態になるため、他工事との並行作業ができるのも超速硬化ウレタン防水工法を採用するメリットのひとつです。
施工時の注意点や養生の必要性は?
超速硬化ウレタン防水は非常に便利な工法ですが、いくつかの注意点もありますので、ここで紹介しておくと、
養生の重要性について
スプレー施工なので周囲に材料が飛散する可能性がありますので、ガラス・壁面・室外機などの養生は必須です。
特に風がある日は、飛散範囲が広がるため十分な対策が必要になることを理解しておいてください。
気温・湿度への対応について
速乾性があるとはいえ、極端な高温や低温環境下では反応にムラが出ることがありますので、5℃未満の気温や湿度80%以上の日は避けるのが無難でしょう。
また冬場には専用の寒冷地仕様材を使うことで対処できますので、状況に合わせた素材選びを行ってください。
施工機器と技術者の重要性について
超速硬化ウレタン防水は専門の機械と技術を持つ業者でなければ施工できません。
業者選びをする際には、超速硬化ウレタンの施工実績が豊富かどうかを必ず確認しておきましょう。
施工技術が未熟な業者や経験が浅い業者を選んでしまうと、超速硬化ウレタン防水工法のメリットを享受できない可能性もあるので、十分に注意してください。
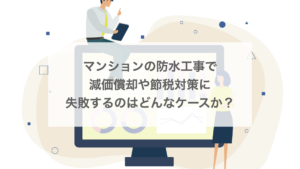
超速硬化ウレタン防水工法のメリットとデメリットは?
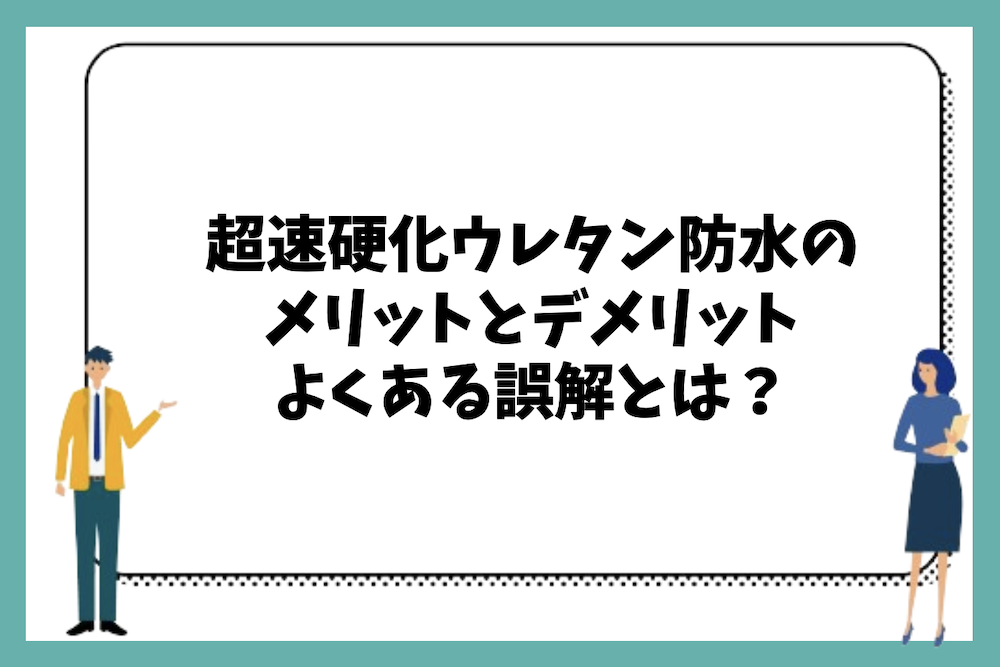
どんな工法にもメリットとデメリットがあり、超速硬化ウレタン防水工法も同じで、そのスピードと密着性に大きな強みを持つ一方で注意点や施工条件も存在しているということ。
実際に施工を検討する物件管理者やオーナーの立場に立って、超速硬化ウレタン防水のメリットとデメリットについて紹介していきます。
またよくある誤解や現場でのトラブル事例も紹介しておきますので、正しい理解を深める際に役立ててください。
超速硬化ならではのメリットは?(工期短縮・密着性・美観など)
超速硬化ウレタン防水には、他の防水工法と比べて際立ったメリットがいくつもありますので、どのような部分で優れているのかというと、
圧倒的な工期短縮│超速硬化ウレタン防水のメリット
- 吹き付け後、数秒〜数分で硬化開始する
- 広い面積も1〜2日で施工完了が可能である
- 施工翌日には他の工事ができる現場も多数ある
これらの特徴によって建物の使用を止める時間が短くて済むため、商業施設・病院・学校などでの導入が進んでいます。
優れた密着性と防水性能│超速硬化ウレタン防水のメリット
- 下地の材質を選ばず強く密着する
- 複雑な形状や段差・配管まわりでも施工が可能である
- 継ぎ目のないシームレスな膜ができるため、水の侵入口が少なく信頼性が高い
美観性と仕上がりの安定性│超速硬化ウレタン防水のメリット
- スプレーによる均一な吹付けで、ムラや段差のない滑らかな仕上がりになる
- 専用機器によって職人の技術差が出にくいため、品質が安定する
環境や安全面への配慮│超速硬化ウレタン防水のメリット
- 無溶剤タイプが多く、施工中の臭いが少ない
- 火気を使わないため、安全性が高い
- 省資源・低廃材で、環境配慮型工法として公共工事にも対応できる
超速硬化ならではのデメリットや注意点は?(費用・機材・小規模には不向きなど)
便利で高性能な工法として人気の超速硬化ウレタン防水にも当然ながら弱点や注意すべき点があります。
事前にマイナス部分を理解しておくことで余計なトラブルを避けることができる可能性がありますので、チェックしておいてください。
初期費用がやや高い│超速硬化ウレタン防水のデメリット
- 材料コストが高価である(高性能な分、単価が上がる)
- ㎡あたり8,000〜20,000円前後が相場で、手塗り型より割高になる
初期費用が高い部分もありますが、工期が短く仮設費用が抑えられるためにトータルコストではむしろ有利になるケースも多い特徴があります。
専用機材と技術者が必要になる│超速硬化ウレタン防水のデメリット
- 施工には2液混合型のスプレー機と発電機など特殊な設備が必要になる
- 取り扱いには資格や経験が求められ、施工できる業者が限られる
誰でも簡単にできる工法ではないので、業者選びが非常に重要なポイントになります。
小規模施工には不向きな場合がある│超速硬化ウレタン防水のデメリット
- スプレー機の準備や片付けに手間がかかる
- 10㎡未満のような小面積ではコスパが合わないこともある
戸建て住宅のベランダなどでは、手塗り型の防水工事の方が現実的な選択肢になる場合もあります。
養生(飛散対策)が必須になる│超速硬化ウレタン防水のデメリット
- 吹付け施工なので、塗料の飛び散りが発生する可能性がある
- 周囲の壁や設備にしっかり養生を施す必要がある
施工環境によっては、近隣への配慮や施工時間の調整も求められることがありますので、学校や病院などが近隣にある際には十分な配慮を行ってください。
よくある誤解やトラブル事例とその回避法は?
現場での誤解や思い込みが原因でトラブルになるケースも少なくないので、超速硬化ウレタン防水の代表的な誤解とトラブルの回避ポイントについても簡単に紹介しておきます。
吹き付けだから誰でも均一に仕上がる│超速硬化ウレタン防水の誤解
回避策:経験豊富な業者に依頼することが重要です。吹付けのスピード、距離、重ね回数など適切な操作が必要なので、業者の技量の影響を受けます。
速く乾くなら、天候も関係ない│超速硬化ウレタン防水の誤解
回避策:最低限の気温・湿度条件は守るべきなので、極端な低温や高湿度では硬化が遅れたり密着不良を起こすリスクがあります。
1回施工すれば30年は安心?│超速硬化ウレタン防水の誤解
回避策:定期的なトップコート再塗布が必要で、最低でも10年に1回程度のメンテナンスを行うことで性能を長期間維持する効果が期待できます。
安い業者に頼んでも同じ│超速硬化ウレタン防水の誤解
回避策:価格だけで判断せずに実績や使用材料、保証内容で比較します。粗悪な施工だと数年で剥がれや漏水の原因になる可能性も否定できません。
この部分を読むことで、超速硬化ウレタン防水工法についてメリットやデメリットも含めて正しく理解してください。
適した場所や条件で採用することで非常に優れた防水性能を発揮する工法ですので、誤解されやすい部分やトラブルの回避方法も理解しておくと安心でしょう。
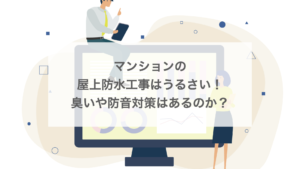
従来工法との違いは?費用や耐用年数、メンテナンス比較
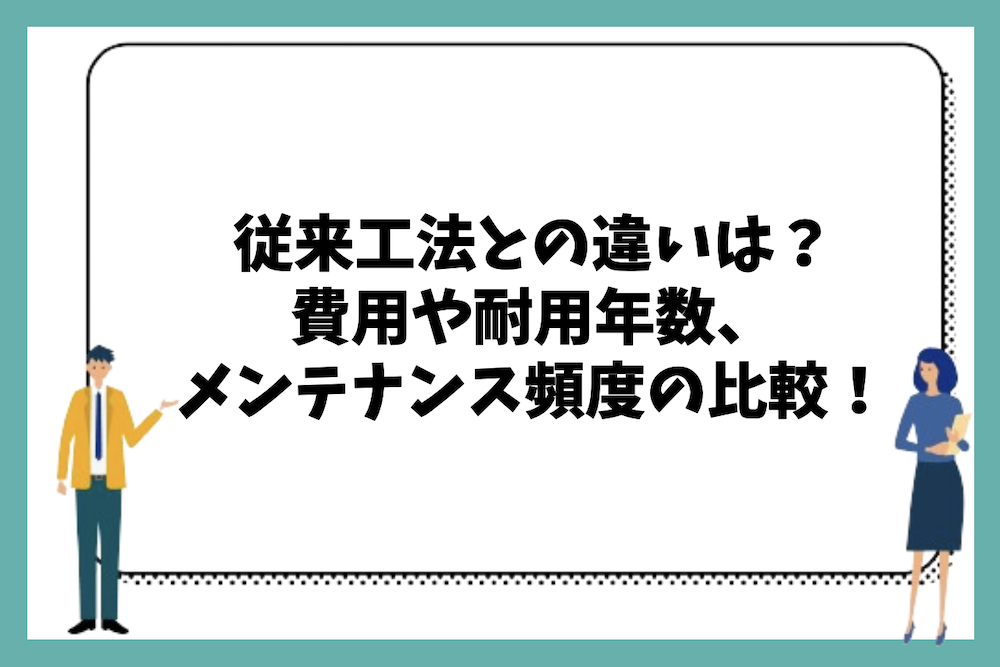
超速硬化ウレタン防水は、従来の防水工法とは見た目も性質も施工方法も大きく異なります。
費用面や耐久性、メンテナンス頻度の違いは、導入を検討する上で非常に重要なポイントではないでしょうか。
一般的なウレタン塗膜防水やシート防水、FRP防水などと比較しながら、超速硬化ウレタン防水がどのような優位性や注意点を持つのかをわかりやすく解説しますので、導入時の参考にしてください。
費用の比較(㎡単価・初期費用・長期コスト)
防水工事を検討する際に、まず最初に気になるのが費用に関する部分ではないでしょうか。
1㎡あたりの単価や長期的に見たコストパフォーマンスに注目して費用に関する情報を紹介していきます。
各工法の一般的な単価(目安)
| 工法名 | ㎡単価の目安(税込) |
| 超速硬化ウレタン防水 | 約8,000~20,000円/㎡ |
| 手塗りウレタン防水 | 約4,000~8,000円/㎡ |
| シート防水(塩ビ・ゴム) | 約4,000~7,000円/㎡ |
| FRP防水 | 約5,000~8,000円/㎡ |
*面積・下地・仕様により変動しますので、あくまでも参考価格だということを理解しておいてください。
費用面のポイント
- 初期費用は超速硬化ウレタンがやや高めになる:専用機材や材料が高性能な分だけ、㎡単価が上がる傾向がある。
- 工期が短いため仮設費・人件費が削減可能:長い目で見るとトータルコストは同等かそれ以下になることも多い。
長期コストを抑えられた事例
- 短工期で済むため、施設の休業や立入制限が最小限で済む。
- 劣化や剥がれが起きにくく、10年以上メンテ不要のケースがある。
- 重ね塗り改修(オーバーレイ)が可能で全面撤去が不要になる。
耐久年数とライフサイクルの違いは?
防水工法の耐用年数は、施工後の性能維持に関わる大きな要素のひとつ。
超速硬化ウレタン防水は材料の進化によって従来の工法と比較しても非常に優れた耐久性を誇っています。
一般的な耐久年数の比較表
| 工法名 | 耐用年数(目安) |
| 超速硬化ウレタン防水 | 約12~15年(適切な施工時) |
| 手塗りウレタン防水 | 約8~10年 |
| シート防水(塩ビ・ゴム) | 約10~15年 |
| FRP防水 | 約10~12年 |
超速硬化型が長持ちする理由は?
- 厚膜で施工できるので物理的な摩耗やひび割れに強い。
- 継ぎ目がなく雨水の侵入口ができにくい。
- 適切なトップコート再塗布で5〜10年は寿命を延ばせる可能性もある。
ライフサイクルの考え方は?
- 1回の施工だけでなく、10年・20年後まで含めた視点で選ぶのが重要なポイントのひとつ。
- 超速硬化型は初期費用が少し高くても、再施工サイクルが長いためコスパが良いと評価されている。
メンテナンス頻度や再施工のしやすさは?
防水工事とは施工したら終わりではなく、定期的なメンテナンスと再施工計画も非常に重要なポイントです。
メンテナンスのしやすさや改修方法の違いについて比較すると、
超速硬化ウレタンのメンテナンス頻度は?
- トップコートの再塗装目安は7〜10年ごとに実施する。
- 本体の防水層は状態が良ければ15年程度は無補修でも可能なこともある。
- 汚れや劣化が軽微であれば重ね塗り(オーバーレイ)で対応できる。
他の工法と比較すると?
| 工法名 | メンテナンス頻度 | 改修のしやすさ |
| 超速硬化ウレタン防水 | △(高性能のため頻度少) | ◎(重ね塗りがしやすい) |
| 手塗りウレタン防水 | △(耐久性はそこそこ) | ○(既存除去が必要な場合も) |
| シート防水(塩ビ・ゴム) | ○(長寿命) | △(一部剥がして再接着) |
| FRP防水 | △(剥がれが早い) | △(下地処理がやや大変) |
管理者にとってのメリットは?
- 定期点検と軽い補修で長期間維持できる。
- 既存を撤去せずに改修可能なケースが多いため管理コストも低減できる。
- ビルやマンションの修繕積立金計画との相性も良い。
ウレタン塗膜・シート防水・FRP防水との比較表
超速硬化ウレタン防水と、よく使われる他の防水工法を一覧で比較しますので、工法選定の参考資料として活用してください。
| 比較項目 | 超速硬化ウレタン | 手塗りウレタン | シート防水 | FRP防水 |
| 施工方法 | スプレー吹付 | ローラー手塗り | シート貼り | 樹脂+ガラスマット塗布 |
| 硬化時間 | 数秒~数分 | 数時間〜1日 | 接着後すぐ | 1日以上 |
| 工期 | ◎ 短い | △ 普通 | △ 普通 | △ 長め |
| 耐久年数 | ◎ 約12〜15年 | △ 約8〜10年 | ○ 約10〜15年 | △ 約10〜12年 |
| 継ぎ目の有無 | ◎ 無し | ○ 少ない | × 多い(シート同士) | △ ややムラが出る |
| メンテのしやすさ | ◎ 重ね塗り可 | ○ 状態次第で可 | △ 一部剥がしが必要 | △ 下地処理が必要 |
| 費用(㎡単価) | △ やや高め | ◎ 安価 | ○ 普通 | △ やや高め |
| 美観・均一性 | ◎ 非常に高い | △ ムラが出る場合あり | ○ 良好 | △ 光沢が出すぎる場合あり |
防水工法を選ぶ際は初期費用だけでなく、維持のしやすさや将来の改修費などの情報も含めて総合的に判断することが重要ですので、上記比較表も参考にして、どの工法が良いのか十分に検討してください。
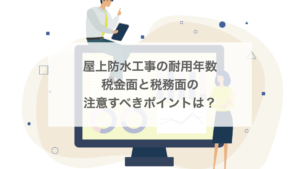
超速硬化ウレタン防水が向いている場所や建物、シーンは何があるのか?
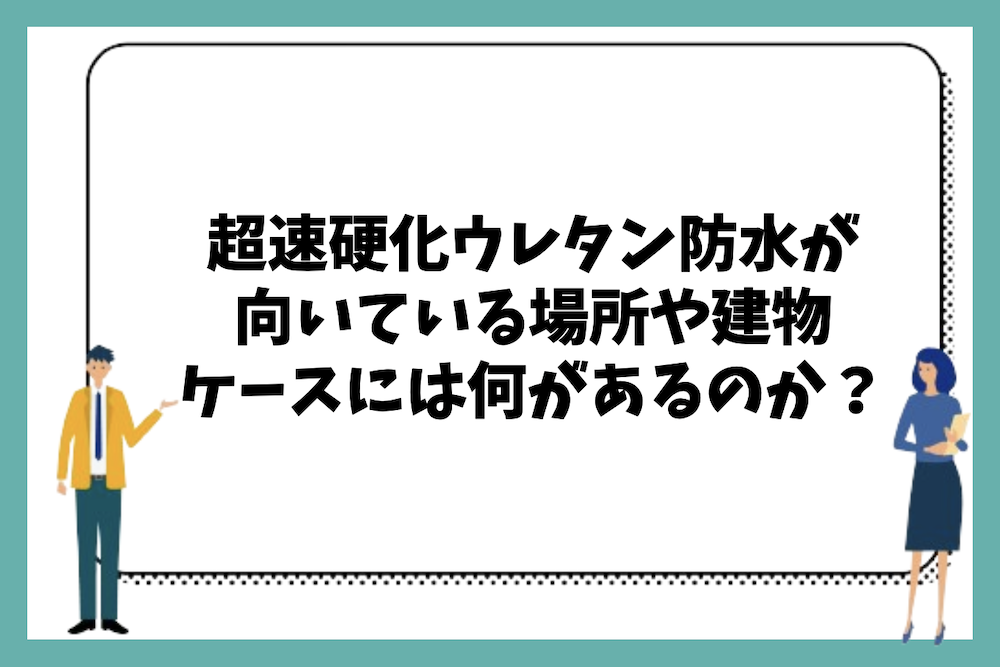
防水工事を検討する際に自分の建物や施設に合うのかという点も非常に重要なポイントのひとつ。
超速硬化ウレタン防水は、そのスピードや柔軟性、高い密着力などを活かして、特定の場所や建物で非常に効果を発揮する工法です。
どんな場所や物件に向いているのか、逆にあまり向いていないケースはあるのかなど、活用シーン別にわかりやすく解説していきますので、参考にしてください。
屋上・バルコニー・機械室などの代表的な施工箇所
超速硬化ウレタン防水は様々な場所で活用できますが、特に下記のような場所との相性は抜群です。
屋上(ビル・マンション・公共施設など)
- 面積が広く、継ぎ目のない施工が可能な点が非常に有利である。
- 雨水が溜まりやすい排水まわりや、段差のある立ち上がり部分にもぴったり密着する。
複雑な構造でも一体化した美しい防水層が形成されますので、防水効果も非常に高い傾向があります。
バルコニーやベランダ
- 人の出入りが多い場所でも速乾性が活きる。(翌日から使用可能な場合も)
- 段差や笠木(かさぎ)といった細かい部分も継ぎ目なくカバーできる
- 無溶剤タイプなら臭いも少なく、居住中でも施工しやすい。
機械室・ピット・配管まわり
- 狭くて施工が難しい場所でも、スプレーなら隅々まで施工できる。
- 湿気や結露が多い場所でも、密着性の高さが効果を発揮する。
水が流れる設備下でも防水性を長く保つ工法として多数の実績があります。
商業施設・病院・学校など短期施工が求められる物件
超速硬化ウレタン防水の工期の短さと速乾性は、営業中の店舗や休みの少ない施設などでも重宝されています。
商業施設・ショッピングモール
- 営業時間外や夜間施工でも翌朝には歩行できる。
- 工事による営業損失を最小限に抑えられる。
病院・福祉施設
- 工事の臭い・音を抑えやすく、患者さんや入居者の負担が少ない。
- 緊急時の工事でも、スピーディーに対応できる。
学校・保育園・公共施設
- 長期休みに合わせて短期間で完了できるためスケジュール管理がしやすい。
- 安全性が高く、火を使わない施工なので安心できる。
超速硬化ウレタン防水が効果的なポイントは?
- 日数制限がある現場で抜群の効果を発揮する。
- 一時的に閉鎖するエリアが限定的で済む。
- 天候の影響を受けにくい工法なので予定変更が少ない。
形状が複雑な箇所や下地が特殊なケースへの対応力は?
スプレー施工が可能な超速硬化ウレタン防水は、形が入り組んでいたり、下地が均一でない場所でもきれいに仕上げられるという非常に大きな強みがあります。
形状が複雑な場所の例は?
- 設備の多い屋上(配管・ダクト・金物のある箇所)
- 段差や立ち上がりのある階段・スロープ
- コンクリートではなく鉄やアルミなどの異種素材が混在する下地
下地が特殊なケースの例は?
- モルタルが劣化し、多少凹凸のあるコンクリート面
- 既存防水がある場所(ウレタンやアスファルトなど)
- 水がたまりやすい傾斜のある場所(排水勾配の少ない屋上など)
このような場所でも、超速硬化ウレタン防水なら継ぎ目のない一体防水が可能だということ。
補強メッシュを使わずとも強度が保てる製品もあるため、手間と費用を抑えながら施工することもできます。
新築と改修、どちらの防水工事に向いているのか?
新築と改修のどちらで使えるのかというのもよくある質問のひとつ。
結論から言うと、どちらでも適応させることができますが、それぞれに特徴があるので、総合的に判断する必要があります。
新築での活用ポイントは?
- 設備や配管の多い屋上やルーフバルコニーでも初期から高い防水性を確保できる。
- 工期の短縮が可能で、他の仕上げ作業と工程を合わせやすい。
- 近年では、公共施設や大型マンションでも採用例が増加しています。
改修(リフォーム)時の活用ポイントは?
- 既存の防水層の上から重ね塗り(オーバーレイ)で改修できる。
- 撤去作業が少なく、廃材処理費用を抑えられる。
- 使用中の建物でも施工できるため、営業や生活への影響が少ない。
どちらにも共通する強みは?
- 新築:高品質な初期防水をスピーディーに実現できる。
- 改修:短期間で確実に防水性能を復旧できる。
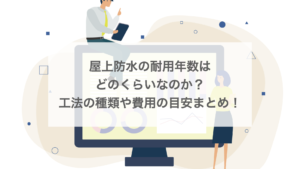
超速硬化ウレタン防水に関するよくある質問(FAQ)まとめ
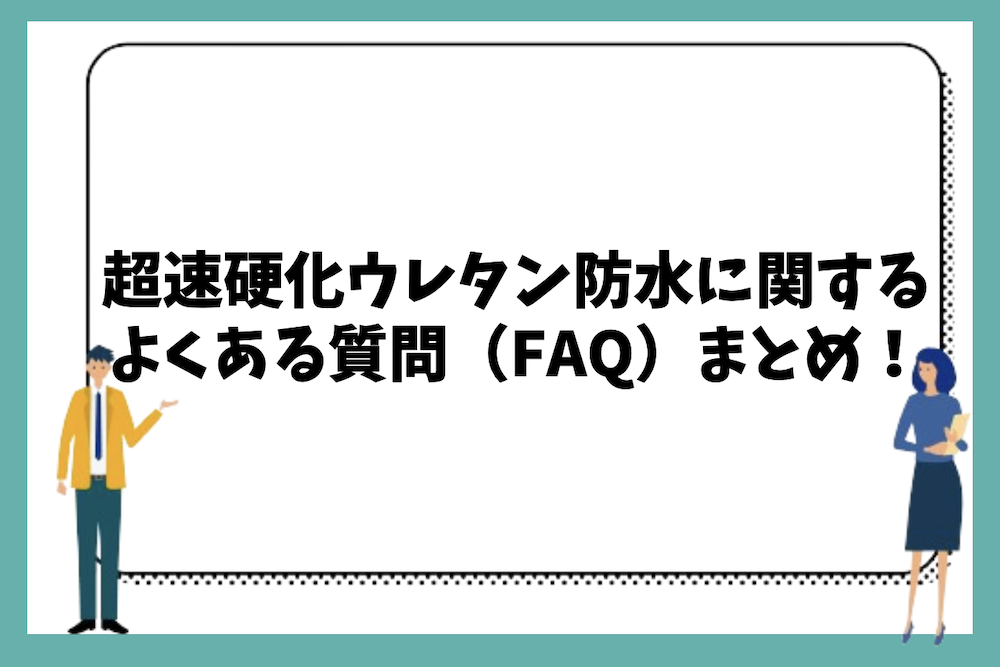
超速硬化ウレタン防水は比較的新しい工法であるため、本当に速く乾くのかとか、耐久性は大丈夫なのか、他の防水工法と何が違うのかなど、多くの疑問や誤解があると思います。
ここでは、建物オーナーや管理者、施工を検討している方が抱えやすいよくある質問をまとめてご紹介します。
超速硬化ウレタン防水を導入しようかどうか悩んでいる人やより詳しい情報を知りたい人はこの項目を参考にして理解を深めてください。
超速硬化ウレタンとポリウレアは何が違うのか?
超速硬化ウレタンとポリウレアはどちらもスプレー式で、吹き付け後に数秒〜数分で硬化する点では共通していますが、材料の性質や施工性に違いがあります。超速硬化ウレタンはウレタン樹脂がベースなので柔軟性と密着性に優れており、建物の動きにも追従しやすい性質があります。ポリウレアはさらに速硬化で高強度・高耐薬品性があり、工場や化学プラントなど過酷な環境での使用が多いです。ただポリウレアは施工温度や湿度の条件が厳しく、専用機材や職人の技術レベルもより高く求められるデメリットがあります。超速硬化ウレタンは、より建築物向けで汎用性が高く、住宅・商業施設・公共施設など多様な現場に対応しやすい部分などが特徴的です。
超速硬化ウレタン防水はなぜ小規模施工に向かないのか?
超速硬化ウレタン防水は、スプレー施工専用の機材を使用するため、機材の設置・調整・清掃などの準備や後処理に一定の時間とコストがかかります。10㎡以下のような小規模現場では、この準備作業の割合が大きくなり、㎡あたりの施工費が割高になってしまいます。吹き付けの際に養生範囲も広く取る必要があるため、ベランダなど狭い場所では周辺設備に塗料が飛散するリスクも高まります。小規模な防水工事では、手塗りのウレタンやFRPなどの簡易的で機動性の高い工法の方がコストパフォーマンスに優れているケースが多くなります。ただ機材や人員の手配に無駄が出ないよう、同じ建物内で複数箇所をまとめて施工できる場合は小規模でもメリットが出ることもあるので、業者に相談しながらどちらの工法が良いのか決定してください。
超速硬化ウレタン防水工法の耐久性は本当に15年以上持ちますか?
超速硬化ウレタン防水は、適切に施工され、定期的な点検とメンテナンスが行われていれば、15年以上の耐用年数を十分に期待できます。実際に各メーカーが実施する促進耐候試験や実環境下での経年劣化データにおいては、10〜20年近く性能が維持された実績が報告されています。長期間効果を維持する際のポイントは、トップコートの定期更新・局所的な剥がれや浮きの早期発見・信頼できる業者による施工です。特にトップコートは防水層を紫外線や摩耗から守る役割がありますので、この層の劣化が放置されると防水層本体にもダメージが及びます。逆にトップコートを7〜10年おきに塗り替えるなど適切に管理すれば、20年以上使用されている建物も実在していますので、効果を持続させたい場合は定期的なメンテナンスをしっかり実行してください。
超速硬化ウレタン防水工事後にトップコートは何年おきに塗り替えればよいのか?
トップコートの塗り替えは、一般的に7年〜10年ごとが推奨されています。トップコートは防水層そのものではなく、その上にある保護層ということもあり、紫外線や熱、摩耗から防水材本体を守る重要な役割を果たしています。時間の経過とともにトップコートは色あせたり、表面が粉をふいたようなチョーキング現象が起こります。これらの状態を放置してしまうと、雨水や紫外線が直接防水層にダメージを与えて、ひび割れや膨れ、最悪の場合には漏水につながる恐れがあります。塗り替えのタイミングを見極めるには、3〜5年おきの簡易点検を行うこと、異常があれば早めに再塗装を検討するようにしてください。遮熱性や耐久性に優れたトップコートを選ぶことでメンテナンス周期をさらに延ばすこともできます。
超速硬化ウレタン防水を重ね塗りで改修するときの注意ポイントは?
重ね塗り(オーバーレイ)による改修は、既存防水層を撤去せずに新たな防水層を上から施工する方法で、コストや工期を抑えられる利点があります。ただ下地の状態を正しく評価しないまま施工してしまうと、数年で剥がれや膨れが起きるリスクがあるため注意が必要です。ポイントは、下地の劣化状況の確認や表面の清掃・研磨処理、適切なプライマーの選定と塗布です。特に既存防水がシート系やアスファルト系であれば、通気緩衝工法を併用して内部にこもった湿気や空気の逃げ道を確保することが求められます。施工前に専門業者にしっかり調査を行ってもらい、下地ごとに最適な工法を選ぶことが長寿命な防水効果を実感するために大切なことなので、専門業者選びもしっかり行ってください。
超速硬化ウレタン防水工事をする日の天気は雨でも大丈夫ですか?
超速硬化ウレタン防水工事でも、基本的に雨天時の施工は避ける必要があります。超速硬化ウレタンは速乾性が高く、湿度にもある程度強い材料ではありますが、吹き付け時に雨水が混入することで密着不良や膨れ、硬化不良などの原因になります。また施工直後に雨が降ると、硬化前の防水層が流れてしまったり、表面に水滴の跡が残ることがあります。安全で高品質な仕上がりのためには晴天もしくは雨の心配がない日を選んで施工するようにしましょう。近年では短時間で硬化するため、施工タイミングを見極めれば雨の合間に作業できる場合もありますが、あくまで経験豊富な業者の判断に委ねる必要がありますので、その点は誤解しないようにしてください。
超速硬化ウレタン防水工事は、他の工事と同時進行できますか?
超速硬化ウレタン防水は、吹き付けから数分〜数十分で表面が硬化して当日中に歩行可能な状態になることも多いため、他の外装工事や屋上設備の設置と並行して工事を行うことができます。商業施設やマンションなどで、短期間で複数の工事をまとめて行う必要がある場合に非常に便利です。ただ吹き付け時は塗料が飛散する可能性があるため、他の業者と作業エリアを調整したり、仮養生を徹底するなどの段取りが重要になります。またトップコートが完全に硬化するまでは重機や重量物の移動には注意が必要なことも忘れないでください。
超速硬化ウレタン防水工事の施工時の臭いはどのくらい気になりますか?
従来の防水材と比べると、超速硬化ウレタン防水は比較的臭いが少ない無溶剤タイプのものが主流となっています。住宅密集地や居住中の物件でも施工がしやすくいと思ってください。ただ施工時に若干の化学臭は出るため、風通しの悪い場所では一時的に換気が必要です。病院や学校などでは施工時間を限定したり、夜間に作業を行うことで臭気対策を行うケースもあります。施工時の臭いが気になる場合は、臭気の少ない製品や低臭トップコートを指定することもできますので、施工前に業者と相談して利用する材料を決定するようにしてください。
超速硬化ウレタン防水工事の費用はトータルで見るとコストは高いですか、それとも安いですか?
超速硬化ウレタン防水は初期費用はやや高めですが、トータルで見るとコストパフォーマンスが非常に高い工法です。超速硬化ウレタンは、施工が速く仮設費用が抑えられるだけではなく、長寿命で再施工の頻度も少ないため、10年や20年と使い続ける前提で考えると非常に経済的だといえます。さらに改修時に既存防水層を撤去せずに上から重ねて施工できるため、解体や廃材処分にかかる費用も削減できます。これらのことを踏まえて、コストだけで判断するのではなく、耐久性・工期・維持管理まで含めて比較することが重要だと思います。超速硬化ウレタン防水は管理コストを抑えたい建物には非常におすすめの選択肢ではないでしょうか。
超速硬化ウレタン防水はどんな下地でも問題なく施工することができますか?
超速硬化ウレタン防水は非常に密着力が高いので、コンクリート・モルタル・金属・既存防水層(ウレタン・FRP・塩ビシートなど)のほとんどの素材に対応することができます。ただどんな下地でもそのまま施工できるわけではなく、下地ごとに行うべき処理があります。たとえば、コンクリート面には下地の凹凸やレイタンス(粉)がないか確認する必要がありますし、金属面では錆を除去した上でプライマー処理を行います。既存防水が劣化して浮いている場合は、部分撤去や補修が必要です。下地の状態を正確に判断せずに施工してしまうと剥がれや膨れの原因になるため、必ず事前調査を行って最適な下処理とプライマーを選定してもらうようにしてください。
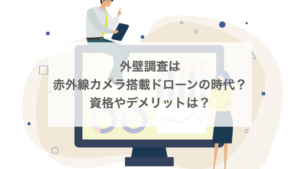
外壁の劣化状態の確認や修繕工事費用の無料見積もりはフェアリノベーション株式会社にお任せください。
マンションやアパートの外壁診断やリフォームに関することであれば、どのような相談でもお受けすることができます。
フェアリノベーション株式会社の外壁診断のおすすめポイント!
- 外壁診断のお見積もりは無料です。
- 訪問なしでお見積もりが可能です。
- 親切丁寧な対応が評判です。
- 疑問点は何度でも相談できます。
将来的な大規模修繕工事や外壁調査を検討されている方でも良いので、現状確認の為にもまずはお気軽にご連絡ください。

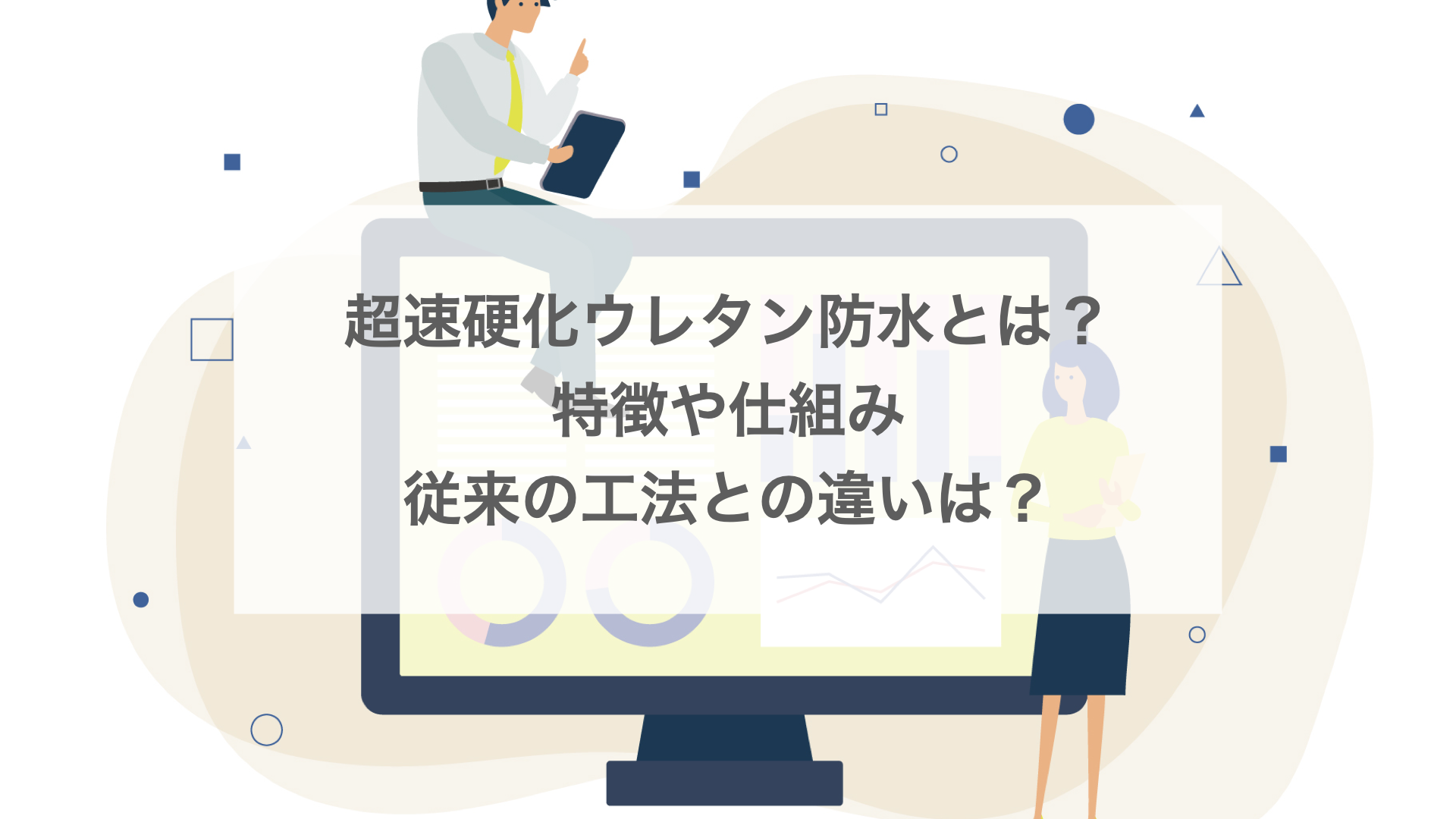
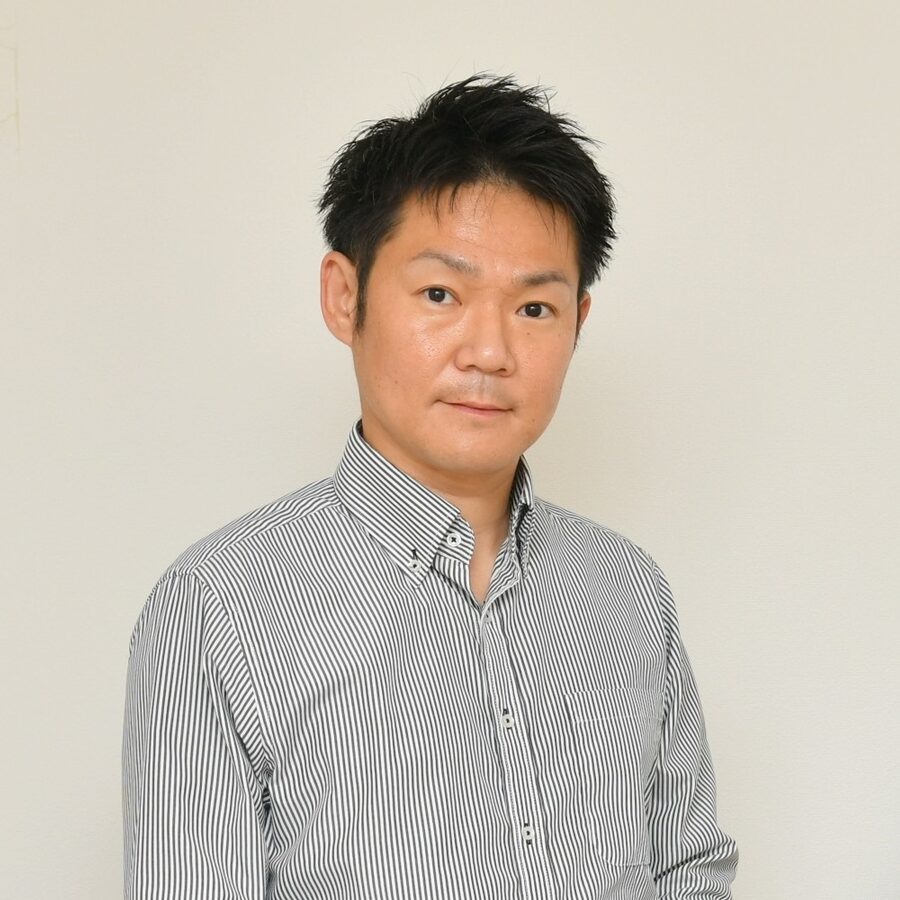
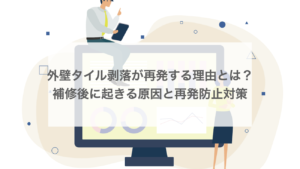
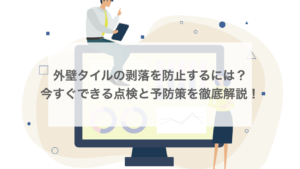
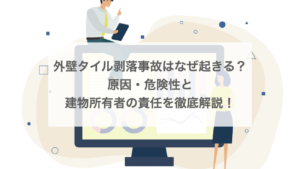
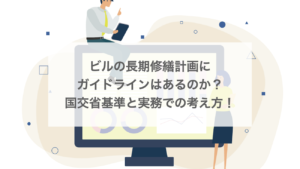
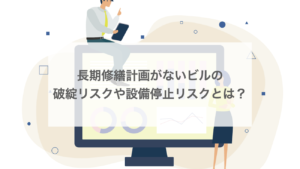
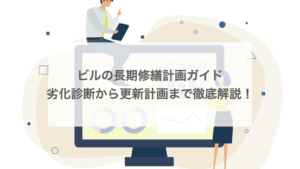
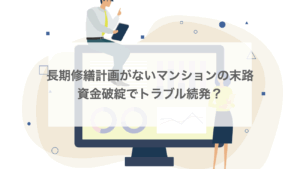
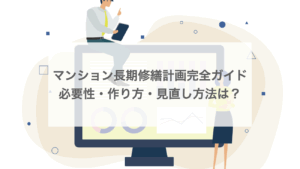
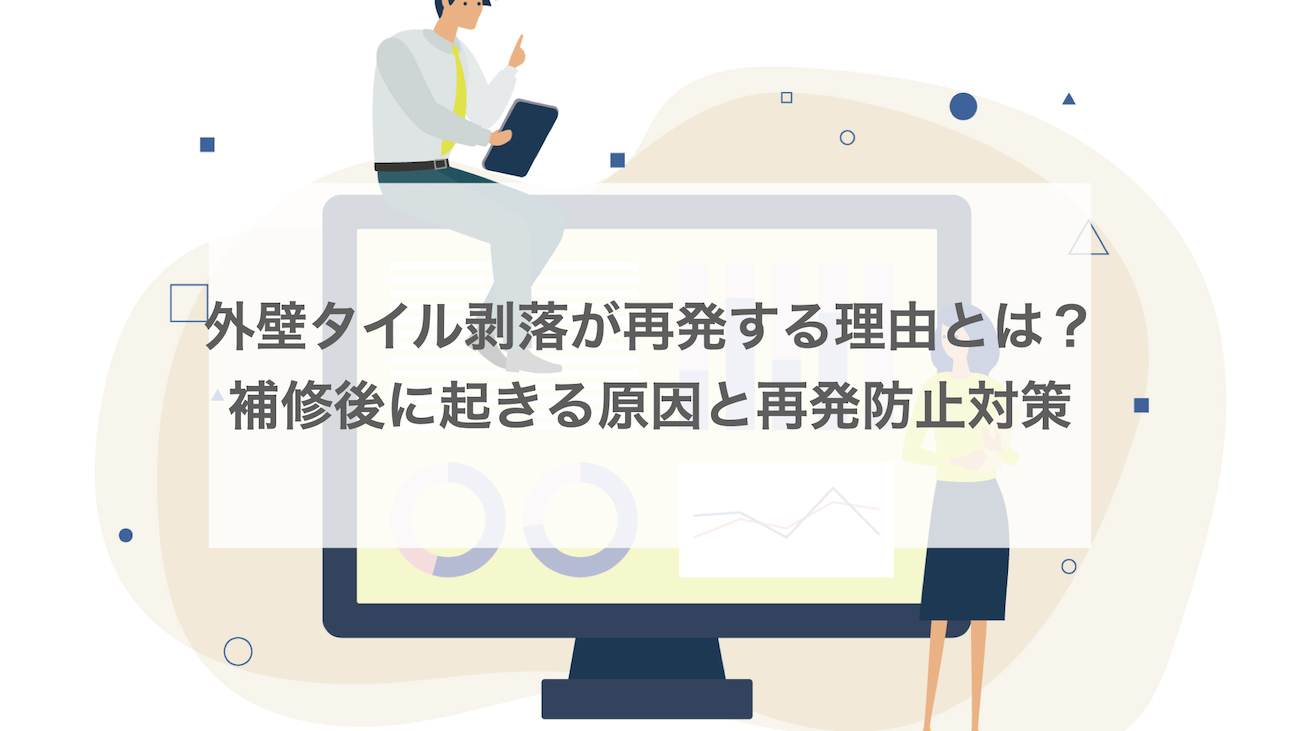
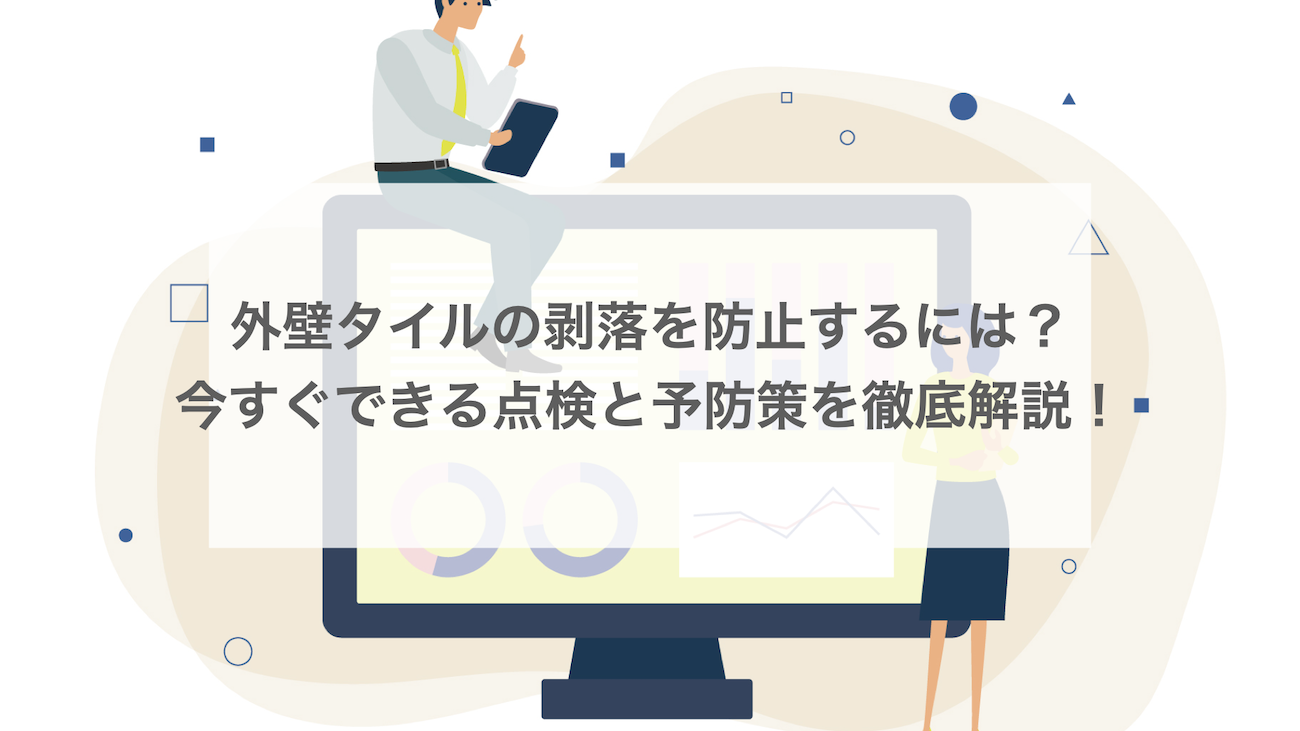
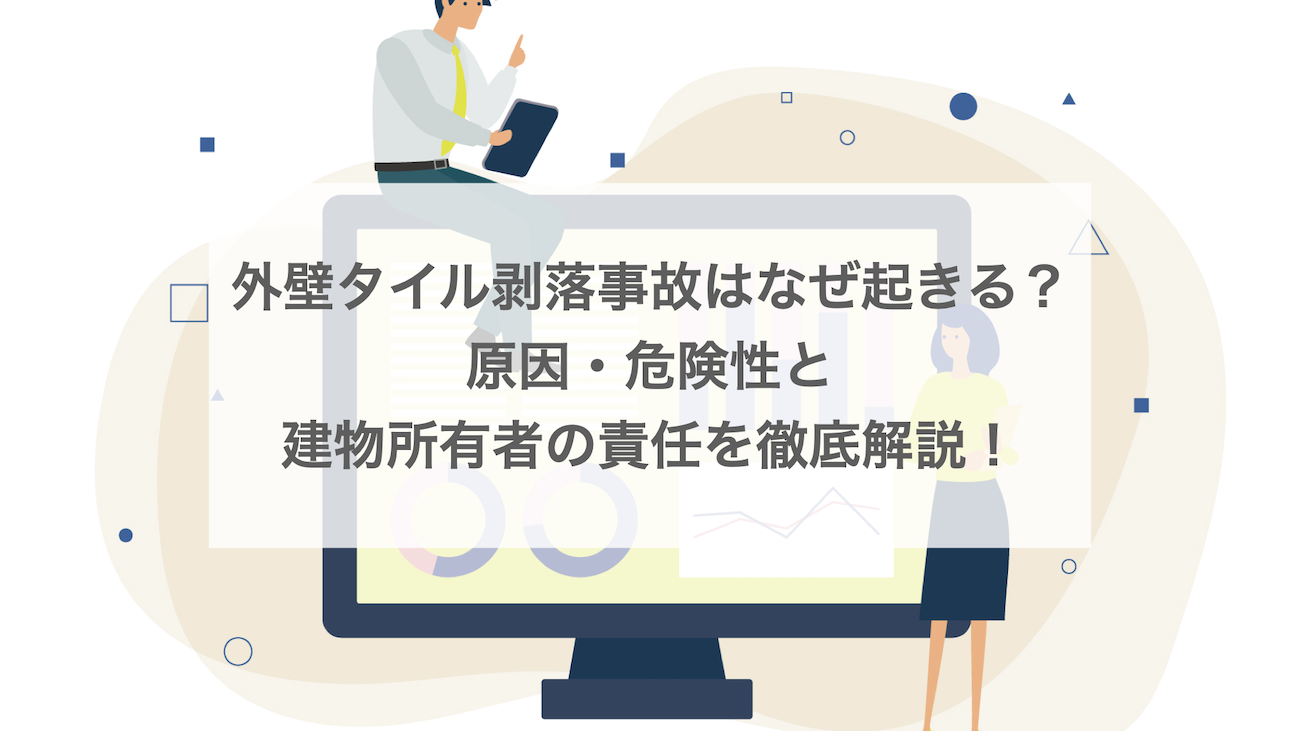
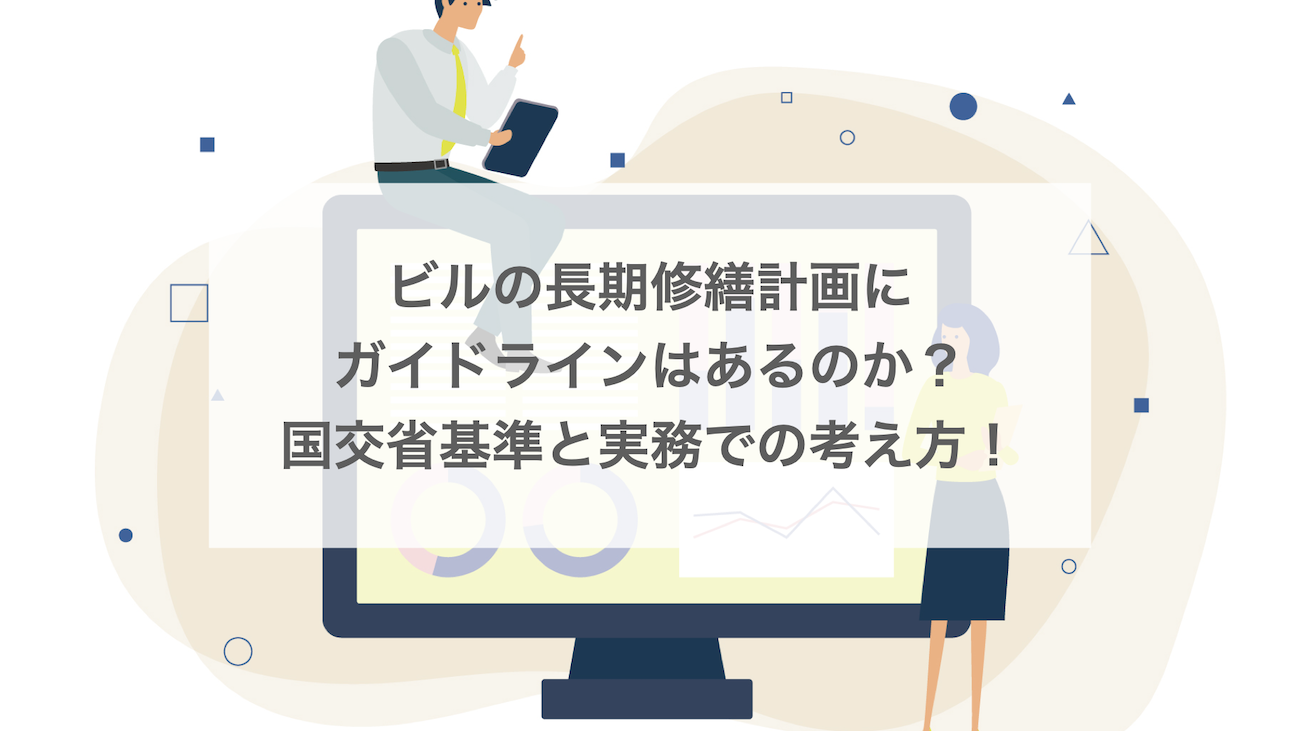

コメント